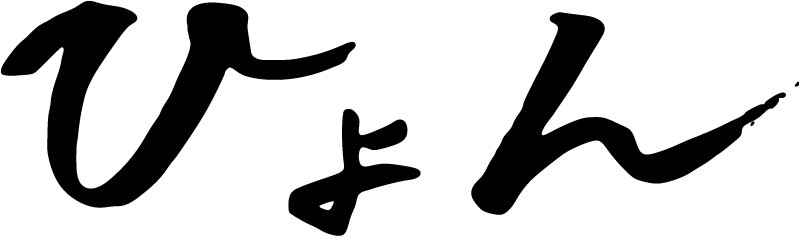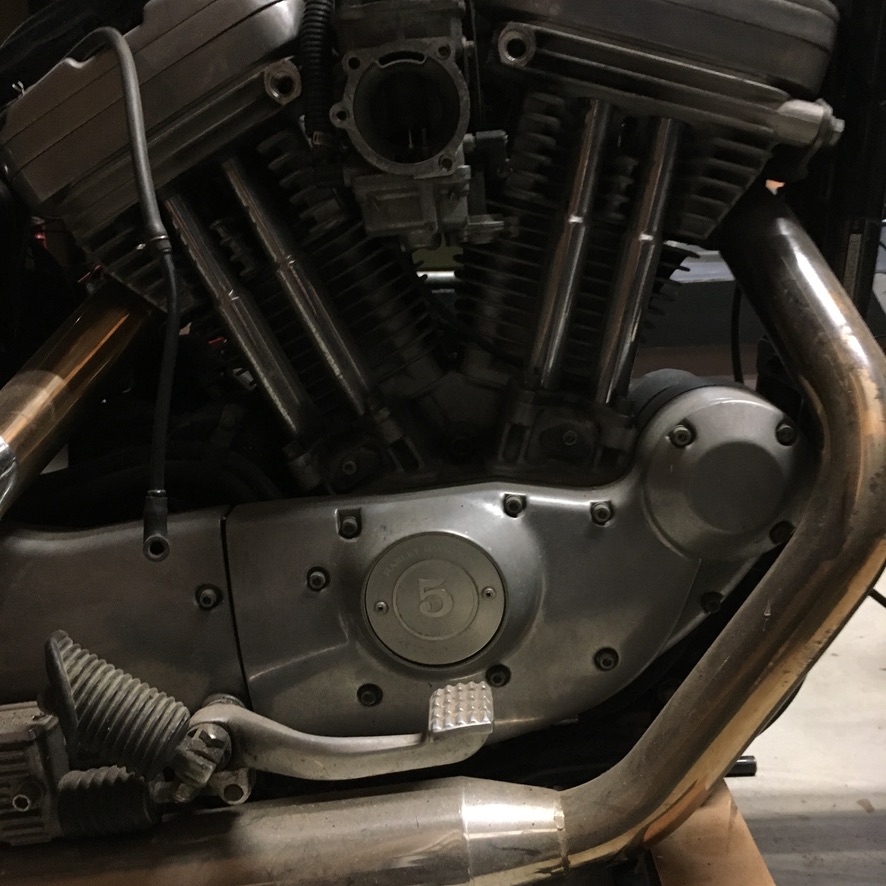ーー小柳帝の映画ゼミ・夏の増刊号ーー
ーー小柳帝の映画ゼミ・夏の増刊号ーー
フランス語とカルチャー、両方を学べるとっておきの教室 ROVA を主宰する小柳帝さんのイベントが、福岡で半年ぶりに開催されます。どうぞご参加ください。
日時:7/27(土) 20:00〜22:00
参加費:一般2000円、学生1500円(当日学生証をご持参ください)
<要予約>
7/25(木)締切
*締切は過ぎましたが、キャンセルが出るなどしましたので、若干名追加募集いたします。
7/27(土) 18:00まで、予約受付け
ご希望の方は、お早めにご連絡ください。
参加希望の方はecole.rova@gmail.com まで、
タイトルを「映画ゼミ参加希望」とし、お名前(フルネームで)、参加人数、代表の方の携帯の番号をお書き添えの上、メールにてご予約ください。
※定員には限りがありますので、お早めにご連絡ください。
会場:organ
=========================================================
「小柳帝のバビロンノート」シリーズの元になった映画ゼミを福岡で開催します!
今回は、今年の新作を観る上で、引いては現代映画を観る上でポイントになるようないろいろなトピックを、雑誌風にアラカルトで、2時間たっぷり語り下ろしたいと思います。
例えば、こんな感じです。
・スローシネマとは?
小柳が今年の初め、ブルータス誌の「睡眠空間学」特集でご紹介した「スローシネマ」。タルコフスキーからドゥヴォス(『Here』『ゴースト・トロピック』)までお話しします。
・フランスのアート・アニメーションの現在
小柳がパンフに寄稿した『リンダはチキンが食べたい』や、サントラ盤の解説を書いた『めくらやなぎと眠る女』など、最近勢いのあるフランスのアート・アニメーション映画についてお話しします。
・2024年は日本の若手によるアニメーション映画の当たり年
今年は、間違いなく日本の若手アニメーション作家による傑作、秀作の当たり年です。『ぼっち・ざ・ろっく!』、『きみの色』などのバンドものを中心に、『ルックバック』、『モノノ怪』などについてお話しします。
・日仏合作映画の未来
このところ、表面的にはわかりにくいものも含め、日仏合作、というか、フランスの会社やスタッフが製作や制作陣に名を連ねる日本映画が増えてきています。合作がわかりやすい黒沢清の『蛇の道』から、わかりにくい奥山大史の『ぼくのお日さま』や、五十嵐耕平の『SUPER HAPPY FOREVER』のような作品までお話しします。
などなど、これから公開される新作情報含め、2時間たっぷりお話しいたします!福岡の映画好きの方は、ぜひorganさんまでお集まりください! (小柳帝)