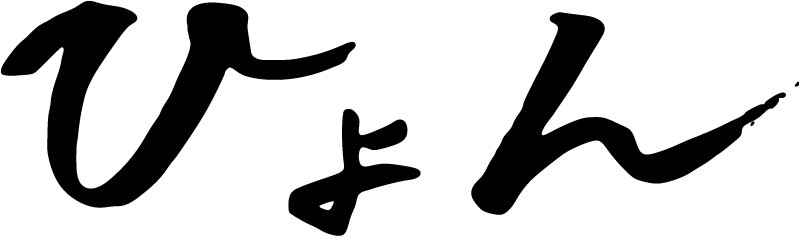年明けから、友人たちの訃報が続いたので、へしゃげた。
みんな60から70歳くらいで、早すぎたという人もいるだろうが、年齢のことではない。人にはそれぞれの寿命がある。ひと昔前なら還暦を越えれば長生きだったろうが、今では80を超えないと人並みではないご時世。プラス20年のハードルは高くないか。
大学で東京にいた頃、間借りしていた高円寺の六畳の部屋に一年に一度、三つ年上のいとこTetsuが訪ねてきてしばらく泊まっていた。諏訪之瀬島という、鹿児島の沖にある小さな島のコミューンから北海道のコミューン村への移動の途中に寄ってくれていた。
Tetsuは大学受験の前夜に突如出奔して四国の寺に行った。でもしばらくすると仏門の道を諦め、その後4,5年をかけて世界一周のヒッチハイク旅へ出た。インドから中東のイスラエルに行き「キブツ」という農業共同体に参加してユダヤ人や世界中からやってきた若者たちと生活を共にした。サハラ砂漠では先住民ベルベルとも暮らした。そして大西洋を渡りアメリカへ。そこで60年代アメリカのカウンターカルチャーの洗礼を受け日本へ戻ったというわけだ。
そんな話を、どちらかというと無口なTetsuは六畳間の万年こたつに座り、静かな口調で少しづつ話してくれた。意外だったのは、僕が当時好きだったThe Bandのレコードを聴かせると「この音楽は聴かないほうがいいよ」などと意味深なことを言ったりもした。彼の大きなオリーブ色のアーミーバッグにはいつもアンリ・ベルグソンの本が入っていた。
そんなある朝、北海道へ向かう彼が「Tシャツを一枚くれないかな。これから北海道は寒くなるのでよかったら…」と言った。それが彼とのお別れになった。諏訪之瀬島で遊泳中に心臓麻痺で亡くなったことを知ったのは、その一年ほど後だ。たしか26歳くらいだったはずだ。
つい最近、突然いなくなったHさんは70年生きた。46年間、Modern Timesというバーのマスターだった。店はカフェバー・ブームもあって、さながら福岡のキャラ立ち人や変人が集まるハイダウェイとなって密かに繁盛した。
「大人になったら一軒でいいから行きつけのバーが欲しい」と思っていた僕にとって、マーヴィン・ゲイやマイケル・フランクスに加えて、ヨーロッパのニューウエイヴィーな音楽を流し、濃くてうまいラムトニックが飲める気のおけない唯一の場所だった。
若きHは文化服装学院を出て、渋谷のBYGというロック喫茶や千駄ヶ谷にあったCul de Sacでバイトをして、1970年代後期の東京カルチャーを経験したひとだった。かといってそれをひけらかすでもなく、ひと懐っこい笑顔で女にモテた。カウンターで、前に付き合った二人と、今付き合っている三人がたまたま一緒だった時は、さすがに焦ったなんて話をしても、嫌味に聞こえない男だった。
店は夕方から朝の3時まで。Hは厨房でカレーライスやナポリタン、オムライスという洋食を作り、馴染みの客が来るとカウンターでそれなりに相手をする。話題は様々で話は尽きない。注文が入るたびに厨房へ消えるが、終わるとまた話に戻った。時に、閉店後まで付き合ってくれたが、最後はいつも「それがなんね、どーしたんね」と、屁理屈をこねる僕に引導を渡してお開きになった。
「長く生きたい」とは欲張りな人間様ならではの欲望だが、そうは問屋が卸さない。「より長く」か「より自分らしく」なのか、その選択は難しい。「死」は向こうからやって来るものだから。ああ、Hの気取りのないオムライスが食いたい。