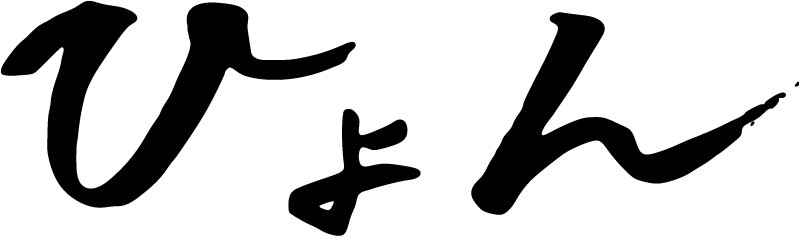藤田嗣治に興味を持ったのは80年代の半ば頃だったか。バブル時代が終りを迎えつつあるというのに、ぼくは”おフランス”への片思い真っ最中だった。きっかけは絵ではなく、おかっぱ頭に丸メガネをかけ、ジロリとレンズに目をやるポートレイト。こんなお茶目な日本人・イン・フランスとあっては、もちろん捨てては置けぬということで、すぐさま下関市立美術館へ駆けつけようやく「猫」や「ヌード」などの実作品に触れた。そして日本画と西洋画がミックスしたような肉感的な線描の素晴らしさにあっけにとられたのであった。それから何度もフランスへ買付に行ったのだけれど、今回ようやく自宅とアトリエを訪れることができた。そしてそこで出会ったのは、Fuojitaの作品にふさわしい暮らしぶりだった。

古い農家の改装を自ら手がけ、気に入る服がないからとミシンを踏み、額縁ももちろん自作、焼き物も作り、日本製の電気釜でご飯も炊いたFoujitaは、みずからをアーティストではなく、アルティザンと呼ぶことにこだわったという。アルティザンとは職人という意味だろう。似た表現の英語にクラフツマンというのもあるが、その場合は似たような製品を手作りするニュアンスがある一方、アルティザンには工夫をこらしたオリジナルをこしらえる一匹狼の趣がある。そんな画家たちがモンパルナスの安下宿で交友を結び、後にエコール・ド・パリと呼ばれる自由で新しい絵画の発展に寄与したのは1910年代、第一次世界大戦直前のことだった。それはパブロ・ピカソ、オシップ・ザッキン、モイズ・キスリング、ジャン・コクトーなどだったのだが、その中でFoujitaが親友と呼んだのはアメディオ・モディリアーニだったことを知り「我が意を得たり」とばかり、ぼくは密かに喜んだ。
何を隠そうモディリアーニは、ぼくが初めて恋に落ちた画家だったのだ。その挙げ句、高校の美術部でモディリアーニ風の油彩画をたった一枚描き上げ、文化祭に出品したところ、あろうことか譲ってほしいという見ず知らずのおじさんのオファーを受けたのだ。どんな絵かというと、当時好きだったマリー・ラフォレの写真をながめつつ、首をやたら長くして、目は灰色で虚ろに、そして両手でりんごを捧げ持たせたもので、青臭い退廃感を醸していたと思う。(お代はいくらだったか忘れたけれど、父に相談の上、確かキャンバスと絵の具代金ほど、つまりメルカリ価格に決定。今思えば、これはぼくのオークション・デビューだったのか)。

それはさておき、丸メガネのアルティザン画家、Foujitaは赤貧の時代から一気に画壇の寵児として、パリっ子の耳目を集めることになる。元来オリエンタリズムに多大な関心を持つフランス人にとって、精緻で美しい線描と乳白色の画面の合体は、さぞかしエキゾティックに映ったことだろう。それにあの自作のアヴァンな服装である。実のところ、そのころのFoujitaはフランス語で「FouFou」と呼ばれる人気者だったらしい。「Fou」といえばゴダールの映画『気狂いピエロ』の原題『Pierrot Le Fou』を思い出す。「クレイジー」というか、日本的には「風狂」というところか。それにも増して、Foujitaがプライヴェートでモダンな感覚を兼ね備えていたことを知ることができたのは、生前の暮らしぶりが保存されたこの家を見学できたおかげだ。
それについてFoujitaは随筆集『地を泳ぐ』のなかでこんなことを述べているので、ちょっと長いけど概略引用してみよう。
「仕事場は仕事本位に、光線は勿論の事設備の万端が、勝手都合宜く出来ていれば物足りる筈で、申し分はないわけであるが、やはり、生活の殆ど一生涯をこの仕事場で暮らすからには、雰囲気を考慮して、自己の趣向を取り入れておきたいのである。(中略)居間から改まった気分で、戦場に臨むような気がしたり、屠殺場にでも行くような、概して日本等の寒い画室陰気な仕事場に、改まって行くという感じが嫌である。生活の延長、生活が流れ込んだ画室、始終いて別に画室にいるという気分のしない仕事場が理想である。華美豪奢は望みたくないのである。余りかけ離れたモダーンも不自然である。(中略)と言って、普通の座敷なり洋室も好ましくないのである。多少風変わりな、自分だけの好みの、特殊の空気がほしいのである。私は田舎家風な、質朴な、頑丈な、散らかしてもいい、汚しても差し支えのない、気のおけない、安心していられる様な仕事場が好きである。」

この、何というのか「反対の反対」をつらぬく独創性が絵に通底しているのは明らかだろう。Foujitaは、当時の日本画壇の主流だった”西洋画もどき”を拒否し、パリにおいて”ジャポニズム”をも拒否し、”自前の”作風を展開したといってもいい。それをハイでポップなスタイルでやっちゃったナウい画家だったわけだ。
ところで、今回日本へ戻ってすぐに『地を泳ぐ』を再読したところ、すっかり忘れていた(というより、30年ほど前にはあまり関心を持っていなかった)画家との交友が記述されていた。猪熊弦一郎である。
Foujitaは、猪熊の芸大の先輩にあたり、パリにやってきた猪熊はモンパルナス、Foujitaはモンマルトルとアパルトマンは離れていたものの、密な交際を続けていて、それは終生変わることがなかった。以下はまたまた長めの引用だが、ふたりのパリぐらしが垣間見えるようだ。
「モンパルナスから猪熊夫妻が、日曜毎に必ず近くの蚤の市に通勤して、この三人のアトリエを順々に訪れてくれる。寧ろ買い物の自慢である、針金細工の大砲やら、古靴下で拵えた鶏やら、南京虫退治の鞴やらを、古新聞紙の包みから一々大事そうに取り出して、おやじさん、どうだい、見てくださいって言うんだ——日本へ持って行きゃ素敵なもんだ、と独り悦に入って見せてくれるが、私達は又額縁を並べ立てて、この演題の客へ一通りのお説教を繰り返さねば胸がすかぬ。」
ドイツ軍が今にもパリへ侵攻してこようかという非常時に、蚤の市で見つけてきたガラクタを披露する猪熊の物好きぶりがブラボー過ぎる。多分、丸亀にある彼の美術館所蔵のコレクションの中にはきっとその時の戦利品が混じっているかと思うと嬉しくなってしまった。
そんな二人のFouがその後、太平洋戦争下で共に「戦争画」を描く羽目になるとは、なんという運命のいたずらか。ましてFoujitaは、戦後の日本で「戦争協力者」のレッテルを貼られてしまう。パリへ戻ったFoujitaは、レオナルド・フジタとしてカソリックの洗礼を受け、その後二度と日本の土を踏むことはなかった。いつだったか、Foujitaが描いた戦争画の一枚「アッツ島の玉砕」をテレビで観たが、鬼気迫る悲壮な形相の兵士たちの姿には、戦争賛美は感じられず、これを見たら、誰しも戦争に参加する気にはなれなかったのではないか、と思った。フジタは後年、このようなことを言っている。
「僕が日本を捨てたのではなく、日本が捨てたのだ」。