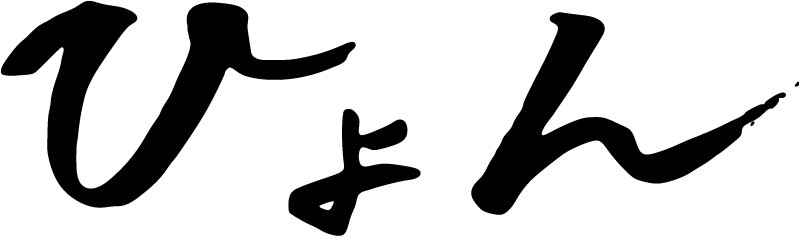タワーレコード時代の友人Sさんから、この前のクリスマスに二枚のCDが送られてきた。一枚はThe Bandのトリビュート盤”The Endless Highway”で、随分前にアメリカで発売されたものらしいのだが、まったく知らなかった。参加しているのは、ほぼ今のアメリカのミュージシャンで、ほとんどが聞いたことがない名前だ。もう一枚はBurt Bucharachの”Blue Umbrella”。「バカラック92歳の新作、絶品です」というSさんのメッセージが添えられていた。
タワーレコード時代の友人Sさんから、この前のクリスマスに二枚のCDが送られてきた。一枚はThe Bandのトリビュート盤”The Endless Highway”で、随分前にアメリカで発売されたものらしいのだが、まったく知らなかった。参加しているのは、ほぼ今のアメリカのミュージシャンで、ほとんどが聞いたことがない名前だ。もう一枚はBurt Bucharachの”Blue Umbrella”。「バカラック92歳の新作、絶品です」というSさんのメッセージが添えられていた。
タワーレコードが日本で輸入盤の卸しとフランチャイズを初めて展開したのは1970年代の終わりころだったか。たしか大阪と金沢、そしてぼくが勤めていた福岡のレコードショップがフランチャイズになったのだが、そのときの担当がSさんだった。東京人らしく一見クールで時々お茶目、アメリカ音楽が好きなひとだったから、商売抜きで仲が良くなった。1、2年経ったころ、Sさんから「渋谷に初の直営店を出すんだけど、売れるかな?」という電話があった。ぼくは「何を仰るウサギさん」と答えた。やがてオープンした店は連日の超満員。でもSさんは、何が気に入らなかったのか、スッタフを総入れ替えしたらしい。やはりアメリカ的なひとだったのかな。
どっちから聴こうかと一瞬迷ったが、今までトリビュートで面白かったものに出会ったことがなかったしと、バカラックにした。すると、1曲めのイントロからあのバカラック節が流れてきた。そしてすぐに極上のセンチメンタルなメロディーが、抑制気味の男性ヴォーカルに乗って耳からハートに染み込んできたからもうたまらない。時間を超えて、すべてのことを慰撫するような音楽、健在すぎるよ、Mr.ソングライター。
バカラックがジューイッシュの家庭に生まれたことが、かれの音楽に与えた影響が何だったのか、僕には知る由もない。でも、感じることはできる。「エグザイル」として「国」という寄る辺がない「孤独」。その対価としての「自由」。アメリカで、このふたつを両立させるのは簡単なことでない。それをアウフヘーベンしたのがバカラックの音楽だったのではないだろうか、なんて。
さて、ザ・バンドだ。あまり期待もせずに聴き終えたら、打ちのめされてしまっていた。The Rochesが歌う”Arcadian Driftwood”や、Jack Johnsonの”I shall be released”など、ベテラン勢も良かったが、なにしろ若手(かどうかしらないけど)にやられた。いづれも原曲を損なわないアレンジ(なかにはグランジやファンキーっぽいバンドもあり、それも良)と演奏、そして歌詞が際立つ素直な歌い方がとても好ましく、オリジナルでは聞き取りにくかった歌詞が立っていて、今の時代にも有効なフレーズが警句のように響く。
1960年代の終わりに出会った”The Weight”という曲は、のっけのギターの印象的フレーズからして、45回転のレコードをあえて33回転でかけたような独特なテンポを持つ、ゾクッとする未知の音だった。そこにはヒッピーの若さはなく、「悟り得ない老人」のような違和感が充満していた。言ってみれば、「進歩」や「新しさ」への疑いであり、カウンターカルチャーに対する批評だった。この曲でリフレインされる言葉がある。
Take a load for free「重荷を下ろして自由になれよ」
そんなザ・バンドの音楽性は、しばらく前から「アメリカーナ」と呼ばれるようになった。たしかに、彼らはさまざまなアメリカのルーツ・ミュージックという「古い」ものを、彼らなりに回復しようとした稀有なロック・バンドだったと思う。「アメリカーナ」とは言ったものの、5人のメンバーのなかで、アメリカ人はドラムスとヴォーカルのレヴォン・ヘルムだけ。残りの4人はカナダ人で、しかも、多くの曲を手掛けたギタリスト、ロビー・ロバートソンはジューイッシュとネイティヴ・アメリカンという他者性が際立つ両親のもとに生まれている。まさにザ・バンドの面々は、アメリカとカナダにまたがるマルチ・カルチャーの落し子だ。そんな彼らにとって、移民たちのルーツ・ミュージックは彼らにとって決して「古い」ものではなかったはずだ。
ザ・バンドとバート・バカラック。とっつきにくいオジサン・バンドと稀代のメロディメーカー。スタイルこそ違え、どちらも「アメリカーナ」を体現していることを思った。
ところで、トランプ大統領は先日、ようやく敗北宣言をした。メキシコとの国境に壁を作ろうとした御仁は去る。これで世界の「重荷」は、一瞬だけ軽くなったのかな。