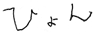Coper & Rie
August 6th, 2010
 猛暑の中、ハンス・コパー展を見るために東京へ行った。ルーシー・リー初期のカップ裏面に並んだふたつのモノグラムを見て以来、あの大きな目をした男が気になって仕方がなかったからだ。よく知られるように、1950年代のコパーはリーにとってなくてはならない存在だった。しかし、リーに比べると日本でのコパーの知名度は低い。
猛暑の中、ハンス・コパー展を見るために東京へ行った。ルーシー・リー初期のカップ裏面に並んだふたつのモノグラムを見て以来、あの大きな目をした男が気になって仕方がなかったからだ。よく知られるように、1950年代のコパーはリーにとってなくてはならない存在だった。しかし、リーに比べると日本でのコパーの知名度は低い。
1956年、コパーはパリにブランクーシを訪ねた(あいにく不在で会えなかったらしいが)。ジャコメッティにも傾倒していたという。なるほど、あのちょっと奇っ怪なフォルムには観念的なものを感じざるを得ない。しかし、実際に作品を目の当たりにすると、様々な技法を凝らしつつ、ほとんどが口と胴体を持っている。まるで、彫刻に肉薄しつつ、ギリギリのところで器として踏みとどまっているかのようだ。そのことを物語るかのように、各作品のキャプションは単に”Bowl”,”Pot”,そして”Vase”となっている。
見終わって、図録を買おうとしたらTシャツを売っていた。一枚は作品の写真、もう一枚のほうはリーとのツーショット。チョット迷った末、後者に決めた。自家用に使っていた中古のロンドンタクシーの運転席から顔を出したコパーにリーが何か話しかけているショットだ。マッシュルームカットのコパーはカメラを見つめ、リーの視線とは交錯していない。まさに、陶芸の世界へ誘ってくれた彼女と別れ、自身の道を走り始めようとするかのようにも見える。
“NO SHIRTS, NO FOOTWEAR, NO SERVICE”
August 1st, 2010
 マウイ島のワイルクというひなびた町にある”世界に名だたる”パンケーキ屋の入り口の窓に「シャツを着ていないひと、裸足のひとはおことわり」の注意書きがあった。そこは町の食堂みたいな場所だった。一方、高級リゾート地カパルアにある店のスタッフが着ていたTシャツの背中には、そんな人でも「ノー・プロブレム」とあった。その一帯がリッツ・カールトン・ホテルの敷地なので、ラフな格好の滞在客を意識したメッセージかもしれない。
マウイ島のワイルクというひなびた町にある”世界に名だたる”パンケーキ屋の入り口の窓に「シャツを着ていないひと、裸足のひとはおことわり」の注意書きがあった。そこは町の食堂みたいな場所だった。一方、高級リゾート地カパルアにある店のスタッフが着ていたTシャツの背中には、そんな人でも「ノー・プロブレム」とあった。その一帯がリッツ・カールトン・ホテルの敷地なので、ラフな格好の滞在客を意識したメッセージかもしれない。
 島全体が観光産業で成り立っているのだろうが、大衆食堂にドレスコードがあって、洒落た店のほうがユルイというのも不思議なものだ。映画『ティファニーで朝食を』のホリー・ゴライトリー嬢なら、さてどっちの店を選ぶだろうか?と思ったらなんだか可笑しかった。アメリカって国は色んな試行錯誤で成り立っている。
島全体が観光産業で成り立っているのだろうが、大衆食堂にドレスコードがあって、洒落た店のほうがユルイというのも不思議なものだ。映画『ティファニーで朝食を』のホリー・ゴライトリー嬢なら、さてどっちの店を選ぶだろうか?と思ったらなんだか可笑しかった。アメリカって国は色んな試行錯誤で成り立っている。
地球が存在していれば
June 18th, 2010
 そういえば、dosaが2005年に出したカタログみたいな写真集も、今回の旅のきっかけのひとつだったのかもしれない。LAを起点に、アジアなど手仕事の美しさを生かした服作りをするクリスティーナ・キムの世界は、どのページも緑深い手つかずの森。ネイティブやヒッピーみたいな欧米人がドリフト・アウェイする様がとても魅力的だった。もっとも、その写真集が撮影されたのはカウアイ島で、今回は水先案内を引き受けてくれる友人がいるマウイ島上陸だったのだが…。
そういえば、dosaが2005年に出したカタログみたいな写真集も、今回の旅のきっかけのひとつだったのかもしれない。LAを起点に、アジアなど手仕事の美しさを生かした服作りをするクリスティーナ・キムの世界は、どのページも緑深い手つかずの森。ネイティブやヒッピーみたいな欧米人がドリフト・アウェイする様がとても魅力的だった。もっとも、その写真集が撮影されたのはカウアイ島で、今回は水先案内を引き受けてくれる友人がいるマウイ島上陸だったのだが…。
マウイ島はアメリカ本土から直行便が出ているほどアメリカ人のフェイバリットらしく、確かにゴルフ場やコンドミニアムなど家族向けのファシリティが整備されていて快適なヴァカンスが約束されている。ビーチはゴミひとつなく、フナムシもおらず、磯臭さもなく、蚊もほとんどいないと来ている。もちろん貿易風が絶えず吹いているから汗もかかない。カナヅチで、海にはいるのがおっくうな僕みたいな人間も、木陰で本などを読むフリをしたりと、まさに言うことナシ(これでキツエンにもう少し寛容だったら、などというのは虫が良すぎる話)。そういえば、ハイウェイを時速45マイルで走っていて前方にとぐろを巻いたかのような物体を発見した奥さんは反射的に声をあげた「ヘビだ!」と。僕は冷静に(友人から聞いたとおりに)、ハワイにはヘビがいない旨を彼女に伝えた。案の定、それはロープだった。
大昔、海底火山が隆起して出来たハワイ諸島には元来ヘビはいないらしい(時々外国船の荷物なんかに紛れ込んで侵入したヘビが発見されると、テレビで話題になるそうだ)。今でも、ハワイ島の南では海底火山が活発な活動を続けており、将来海上に隆起して島になると考えられている。ただし、それは数万年後の未来であり、地球が存在していればという条件付きである。
HONOHONOすれば気分はALOHA,皆さんMAHALOです。
June 5th, 2010
 オアフ島へは随分昔に一度だけ格安ツアーで訪れたことがある。「ハワイなんて、どうせ芸能人御用達のパラダイス」とタカをくくっていたのだが、カラッとした空気と絶え間なく吹く風は、思いのほか気持ちが良かった。そもそもきっかけとなったのはスラッキー・ギター。ハワイアン・ミュージックでよく使われるオープンチューニングしたギター奏法である。なかでもサニー・チリングワースのCDには、仕事とプライベートの両方に行き詰まり、毎日酒浸りでくさりきっていた時期、いわば睡眠導入剤として随分お世話になったものだ。ゆるめのチューニングによる「ボヨーン」というレイジーな弦の響きと、ハワイアン・カウボーイらしい男気あふれる泣き節に、恥ずかしながら癒されてしまい、とりあえず現場を見たくなったのだ。とはいっても、3泊5日のオアフ滞在中には結局スラッキーのライブに遭遇することは出来ず、今回のマウイで初体験を期したわけなのである。
オアフ島へは随分昔に一度だけ格安ツアーで訪れたことがある。「ハワイなんて、どうせ芸能人御用達のパラダイス」とタカをくくっていたのだが、カラッとした空気と絶え間なく吹く風は、思いのほか気持ちが良かった。そもそもきっかけとなったのはスラッキー・ギター。ハワイアン・ミュージックでよく使われるオープンチューニングしたギター奏法である。なかでもサニー・チリングワースのCDには、仕事とプライベートの両方に行き詰まり、毎日酒浸りでくさりきっていた時期、いわば睡眠導入剤として随分お世話になったものだ。ゆるめのチューニングによる「ボヨーン」というレイジーな弦の響きと、ハワイアン・カウボーイらしい男気あふれる泣き節に、恥ずかしながら癒されてしまい、とりあえず現場を見たくなったのだ。とはいっても、3泊5日のオアフ滞在中には結局スラッキーのライブに遭遇することは出来ず、今回のマウイで初体験を期したわけなのである。
事前の下調べでは、予約したコンドミニアム近くのホテルで毎週水曜日にスラッキー・ショーが行われているという。マウイにはスラッキーの名手が多いことは友人のKさんから聞いていたし、今回はまちがいなく生の演奏が味わえるはずだと胸が躍った。おまけにその友人が絶対食べて欲しいというランチプレート屋さんがあり、そのオーナー(サーファー&スラッキー奏者の日本人)に詳しいことを聞くように、と仰せつかってもいるので鬼に金棒だった。目印のピンク色のランチ屋台で総菜各種盛りのボックスをゲットし、翌日のショーの予約をお願いした。ショーのホストを務めるジョージ・カフモクさんはハワイを代表するスラッキーの名人らしいのだ。
そして当夜、コンドからビーチを10分あまりHONOHONOして会場に到着した。この季節限定、パッションフルーツ入りの地ビールをひっかけて準備万端だ。入り口で予約の件を伝えようとしていると、恰幅のいいアロハ姿の男性から「ノブの友人か?」と 声を掛けられた。なんとカフモク氏本人である。そのうえに今夜は招待しますとのこと。ランチ屋台のノブさんの好意に甘えることにした。肝心のライブだが、12弦ギターによるゆったりとした演奏に夢見心地の気分。そのうちに、本当にコックリコックリとなってしまった。やっぱり睡眠導入の効果てきめんなのだ。でも、会場で購入した最新盤CDは、帰国しても連日のように店の中をALOHAな気分で満たしてくれている。MAHALOです。
カマイナ
June 3rd, 2010
 少し前 kama Ainaという日本の音楽ユニットが好きで、マウイ島で録音されたというそのゆったりとしたサウンドを聴きながら、いつか行ってみたいと思っていた。だから、オアフ島から小さな双発機を乗り継ぎ、島に着いてまず友人に尋ねたことはその名前の意味だった。「波乗りをするために、ちょっとマウイへ行ってきます」といって福岡を出発し、そのまま住み着いてしまった彼と再会するのは20年以上振りのこと。「カマイナ? そう、地元の人っていう感じですかね」と教えてくれたその友人は、僕の記憶通りの真っ黒に日焼けした顔と人なつっこい笑顔だった。その昔, 捕鯨(食用ではなく、あくまでランプ用の油をとるためと聞き唖然!)で栄え、ハワイ全体を統治したラハイナという町をブラブラしながら、ふたりで少しづつ思い出話をしたりした。その頃の僕は、カウンターカルチャーみたいなものにあこがれを持ってはいたものの、サーファーには冷ややかだったと思う。ウッドストック派と呼ばれる内省的なミュージシャンとは違い、波乗り野郎なんてきっと快楽的なことばっかり考えている連中に違いないと、なかば反感さえ持っていた。そんな僕も、福岡へ戻って少しづつ友人ができ始め、若いサーファー達と一緒に酒を飲む機会が増えるにつれて考えが変わった。「結局、ヒッピー・ムーヴメントの正当な継承者はサーファーかもしれない」と独り合点したわけだ。
少し前 kama Ainaという日本の音楽ユニットが好きで、マウイ島で録音されたというそのゆったりとしたサウンドを聴きながら、いつか行ってみたいと思っていた。だから、オアフ島から小さな双発機を乗り継ぎ、島に着いてまず友人に尋ねたことはその名前の意味だった。「波乗りをするために、ちょっとマウイへ行ってきます」といって福岡を出発し、そのまま住み着いてしまった彼と再会するのは20年以上振りのこと。「カマイナ? そう、地元の人っていう感じですかね」と教えてくれたその友人は、僕の記憶通りの真っ黒に日焼けした顔と人なつっこい笑顔だった。その昔, 捕鯨(食用ではなく、あくまでランプ用の油をとるためと聞き唖然!)で栄え、ハワイ全体を統治したラハイナという町をブラブラしながら、ふたりで少しづつ思い出話をしたりした。その頃の僕は、カウンターカルチャーみたいなものにあこがれを持ってはいたものの、サーファーには冷ややかだったと思う。ウッドストック派と呼ばれる内省的なミュージシャンとは違い、波乗り野郎なんてきっと快楽的なことばっかり考えている連中に違いないと、なかば反感さえ持っていた。そんな僕も、福岡へ戻って少しづつ友人ができ始め、若いサーファー達と一緒に酒を飲む機会が増えるにつれて考えが変わった。「結局、ヒッピー・ムーヴメントの正当な継承者はサーファーかもしれない」と独り合点したわけだ。
彼が、最初はアメリカ本国へ行くつもりでちょっとマウイへ寄り道したところ、あまりに居心地が良くて「ここでいいか!」とアルバイトをはじめ、気がつけば2度の結婚を経てふたりの娘を育てる父となったことは、なんとなく知ってはいた。それにしても、イタリア系アメリカ人である最初の奥さんとの間の娘は今や海兵隊員で、死別した日本人の奥さんとの娘はもうすぐ高校生だと聞き、ビックリした。その娘はおばあちゃんがいる東京の学校へ進学するためマウイを離れるらしく、ちょうどお別れパーティーをやるから良かったら来て欲しいとのことだった。夕刻にマンションへ伺うと、リビングルームでは彼女の友人達が集まりワイワイやっていた。冬にはクジラが見えるというベランダに腰掛け、彼がポロッと独りごちた。「この島では混血が普通なんです。混ざってない方が珍しいかも…」。たしかに、娘の友人達の顔には色々なオリジンが透けて見える。日本、中国、フィリピン、スペイン、ベトナム、エトセトラ。しかし、ここではみんなカマイナ、国家なんていう括弧にはくくれそうにない笑顔がゴージャスだった。
「音のある休日」#24
May 21st, 2010
TIMELESS / BOBBY CHARLES “ミュージシャンズ・ミュージシャン“という言葉がある。「音楽家から愛される音楽家」という意味合いで、一般的には知名度が低い場合も多い。この遺作を聴き、ボビー・チャールズもそんなひとりだったと思った。
“ミュージシャンズ・ミュージシャン“という言葉がある。「音楽家から愛される音楽家」という意味合いで、一般的には知名度が低い場合も多い。この遺作を聴き、ボビー・チャールズもそんなひとりだったと思った。
1938年ルイジアナ生まれ。ニューオリンズ音楽の作曲家としてレイ・チャールズなどにも曲を提供した白人ミュージシャンである。70年代にはウッドストックに移り、ザ・バンドのメンバーたちと発表したアルバムは「隠れた名盤」として聴き継がれている。その中の一曲「スモールタウン・トーク」は、はっぴいえんどで知られる曲「風をあつめて」の元ネタとも言われている。あの、くぐもった暖かいヴォーカルがもう聴けないと思うと、残念だ。
(西日本新聞5月9日朝刊)
「音のある休日」#23
May 21st, 2010
The Fabric [Post Foetus]
 曲を作り、人前で演奏し、CDを出すのはプロの仕事だった。ところが最近、あの急速に利用者が増えているtwitter(ツイッター)のように、自分なりの「つぶやき」がそのまま音楽となり、フツーに世界中の人と共有できる時代になってきたようだ。
曲を作り、人前で演奏し、CDを出すのはプロの仕事だった。ところが最近、あの急速に利用者が増えているtwitter(ツイッター)のように、自分なりの「つぶやき」がそのまま音楽となり、フツーに世界中の人と共有できる時代になってきたようだ。
ロサンゼルス生まれ、4才の時からクラシック・ピアノを習得した青年が20才でデビュー。聴いてみると、自分なりの音を重ねるという、純粋な楽しさに満ちあふれた美しい作品だった。音を感じ取り、自分なりに表現する。そこには、様々なジャンルの音楽がちりばめられている。彼にとってのノートブック・パソコンは、受け手から発信者へ変わるための大切なプライベート・スタジオなのだ。
(西日本新聞4月25日朝刊)
「〜も、カマタリ…」
May 20th, 2010
 「YODEL」という同人誌めいたフリーペーパーを始めたおかげで、毎日が加速度を付けた勢いで過ぎ去ってゆく。6月発行予定の次号でさえまだちゃんとメドが立っていないのに、気持ちは9月号に飛びかけている。コーヒーに関するコンテンツに決めてはみたものの、知らないことだらけ。焼き付けばでもいいから、コーヒーのイロハが教われないかと、休憩時間に「手音」を訪ねた。今年初のアイスコーヒーを飲みながら、村上さんに質問してみたくなったからだ。「”コーヒールンバ”で唄われる『〜モカ、マタリ….』っていう言葉だけど、モカはなんとなくコーヒーの品種だと分かるとしても、マタリもそうなんだろうか?」。僕が西田佐知子の唄ったこの曲にクラクラしたのは中学生だった頃。鼻にかかった独特の節回しが鮮烈で、リズムがエキゾチックだった。ところが、唄っている内容が摩訶不思議。まだ、ちゃんとしたコーヒーなどほとんど飲んだことがなかったわけで、まるで「判じ物」だったが、かえってそれも惹き付けられた理由だったような気がする。その頃日本史の授業で暗記したばかりの藤原鎌足(もしくは藤原釜足!)のせいなのか、「〜も、カマタリ…」と聞こえてしまったのも仕方がないことだった。「マタリっていうのは、コーヒーの原産地のひとつイエメンに昔あった港の名前です」と、村上さんから聞いて、積年の謎がようやく解けた思いがした。そのうえに「よかったらコレを読んで見てください」ということで、「こうひい絵物語」という本を貸してくれた。版画と文章でコーヒー小史を学べる本のようで、読むのが楽しみだ。
「YODEL」という同人誌めいたフリーペーパーを始めたおかげで、毎日が加速度を付けた勢いで過ぎ去ってゆく。6月発行予定の次号でさえまだちゃんとメドが立っていないのに、気持ちは9月号に飛びかけている。コーヒーに関するコンテンツに決めてはみたものの、知らないことだらけ。焼き付けばでもいいから、コーヒーのイロハが教われないかと、休憩時間に「手音」を訪ねた。今年初のアイスコーヒーを飲みながら、村上さんに質問してみたくなったからだ。「”コーヒールンバ”で唄われる『〜モカ、マタリ….』っていう言葉だけど、モカはなんとなくコーヒーの品種だと分かるとしても、マタリもそうなんだろうか?」。僕が西田佐知子の唄ったこの曲にクラクラしたのは中学生だった頃。鼻にかかった独特の節回しが鮮烈で、リズムがエキゾチックだった。ところが、唄っている内容が摩訶不思議。まだ、ちゃんとしたコーヒーなどほとんど飲んだことがなかったわけで、まるで「判じ物」だったが、かえってそれも惹き付けられた理由だったような気がする。その頃日本史の授業で暗記したばかりの藤原鎌足(もしくは藤原釜足!)のせいなのか、「〜も、カマタリ…」と聞こえてしまったのも仕方がないことだった。「マタリっていうのは、コーヒーの原産地のひとつイエメンに昔あった港の名前です」と、村上さんから聞いて、積年の謎がようやく解けた思いがした。そのうえに「よかったらコレを読んで見てください」ということで、「こうひい絵物語」という本を貸してくれた。版画と文章でコーヒー小史を学べる本のようで、読むのが楽しみだ。
久住登山
May 5th, 2010
 「一泊二日で久住登山をしよう」と最初に友人から誘われたのは確か去年だった。彼はそのコースを子供と愛犬を連れて踏破したばかり。僕も中学生時代に父と一緒に登ったことがある1786mの(ほぼ)九州本島最高峰という山である。さっそくENOUGHのみんなに提案したが、反応がはかばかしくない。ところが、その後同人誌を発行することになりタイトルを「YODEL」、第一号のテーマを「山」などとしたおかげで、少しずつ山への興味が芽生えかけていた。まあ、何事もタイミングが大事ってこと。晴れて今回、13才から61才まで総勢11名プラス犬二匹の即席パーティーで頂上を目指すことになった。
「一泊二日で久住登山をしよう」と最初に友人から誘われたのは確か去年だった。彼はそのコースを子供と愛犬を連れて踏破したばかり。僕も中学生時代に父と一緒に登ったことがある1786mの(ほぼ)九州本島最高峰という山である。さっそくENOUGHのみんなに提案したが、反応がはかばかしくない。ところが、その後同人誌を発行することになりタイトルを「YODEL」、第一号のテーマを「山」などとしたおかげで、少しずつ山への興味が芽生えかけていた。まあ、何事もタイミングが大事ってこと。晴れて今回、13才から61才まで総勢11名プラス犬二匹の即席パーティーで頂上を目指すことになった。
朝6時半に福岡を出発、快晴の山並みを抜け、2時間くらいで6合目の登山口に到着。ここから自力で登る時間は片道4時間ほどらしい。前の晩ライブで一睡もしていないサックス青年は、なんとコンバース穿きで参加。再三にわたる友人の事細かな事前メールにも関わらず、みんな「まあ、なんとかなるさ」くらいの読みだったようだ。ところが、車を降り、いざ登り初めると早速心臓破りの急な坂。まもなく、キャドと格闘していたであろう夜型人間のひとりが早くも音を上げた。早速一回目の休憩。「こまめに水分を補給して下さい」というリーダーの言葉に、もはや汗だくのパーティー一行はゴクゴクと水を体内に注入する。もちろん、その後、いつ果てるとも知らない大小の石ころだらけで急峻な山道と格闘する羽目になるとも露知らず…。
「神経を集中して歩いてください」との声に励まされながら、なんとかその日の宿泊地である温泉へたどり着いた時は、さすがにホッとした。もう、しばらく石は見たくもない気持ちだった。下りは特に膝に負担がかかるようで、たかだかの段差さえ、おっくうである。なんとか落伍者にならずに済んだのは、途中で足にしっかりテーピングをしてもらったおかげだろう。そうそう、軽量ステッキも貸してもらったし、なによりデイパックを替わりに背負っても頂いた。サイコーレーシャとして、遠慮なくご厚意に甘えたわけである。トレッキングシューズを脱ぎ、さて温泉に浸かって疲れを取ろうかと思ったら、膝から太ももへかけて派手に十文字に貼られたテープが現れた。バリバリと剥がしてヌル目のお湯に浸かると、山の夕暮れが、すぐそこまで迫っていた。
「電波OKのところを見つけました」
April 24th, 2010
 今年の春は雨がちで寒かったり、なんだか憂鬱な天気が多かった。春って、実はとてもシンドイ季節だと思う。花咲き乱れ、希望に胸ふくらむ季節なんて言われるが一概にそうとはいえない。「春に逝く」という言葉があるように、いなくなってしまう人も案外多いからだ。父も母も亡くなったのは3月だし、友人の1人もそうだった。それなりの年齢だった父や母の場合は仕方がないが、僕より少しだけだが若かった友人の、それも突然の死はけっこう応えた。エッセイなんかで「親しい友が、先に逝ってしまうことの悲しさ」みたいな文章を知ってはいたが、いつしか自分もそんな年齢になってしまったのだと思い知らされた。ところが、あろうことか、その友人の4回忌に当たる日に、もうひとりの友人が逝ってしまった。二人はお互い友人で、病気が見つかったのも同じ3年前。2ヶ月とあまりに呆気なかった友人に対して、彼は3年間がんばったのだが、それにしても同じ命日になってしまうとは何とも不思議だ。カメラマンだった彼は旅とシャンペンが好きで、その柔らかい物腰で女性に優しかったし、パリではゲイにもモテた。20年以上前、初めてバリ島へ行ったのも彼の薦めがあったからだ。仕事をからめて旅をする名人で、「好きなことしかやらない」というスタンスがみんなからも羨ましがられていたものだった。そんな彼が手術も出来ないほどの病巣をかかえ、幼い子供達へ少しでも思い出を残そうとマウイ島へ行くと聞き、スゴイなーと思ったのは去年の夏のことだった。ほぼ毎日アップされる彼のブログからは、大好きだった海をじっと眺める様子がうかがえた。最後のブログは亡くなる一週間前。ちょっと不思議な言葉が残されていた。「電波OKのところを見つけました。ちょいと離れていますが、、、。とにかく、これでバッチ・グーです」。新しもの好きで、誰よりも早くi Phone を手に入れていた彼のこと、きっと彼岸でも素敵なWiFi環境を見つけたに違いない。まれに見るオプティミストよ、さようなら。
今年の春は雨がちで寒かったり、なんだか憂鬱な天気が多かった。春って、実はとてもシンドイ季節だと思う。花咲き乱れ、希望に胸ふくらむ季節なんて言われるが一概にそうとはいえない。「春に逝く」という言葉があるように、いなくなってしまう人も案外多いからだ。父も母も亡くなったのは3月だし、友人の1人もそうだった。それなりの年齢だった父や母の場合は仕方がないが、僕より少しだけだが若かった友人の、それも突然の死はけっこう応えた。エッセイなんかで「親しい友が、先に逝ってしまうことの悲しさ」みたいな文章を知ってはいたが、いつしか自分もそんな年齢になってしまったのだと思い知らされた。ところが、あろうことか、その友人の4回忌に当たる日に、もうひとりの友人が逝ってしまった。二人はお互い友人で、病気が見つかったのも同じ3年前。2ヶ月とあまりに呆気なかった友人に対して、彼は3年間がんばったのだが、それにしても同じ命日になってしまうとは何とも不思議だ。カメラマンだった彼は旅とシャンペンが好きで、その柔らかい物腰で女性に優しかったし、パリではゲイにもモテた。20年以上前、初めてバリ島へ行ったのも彼の薦めがあったからだ。仕事をからめて旅をする名人で、「好きなことしかやらない」というスタンスがみんなからも羨ましがられていたものだった。そんな彼が手術も出来ないほどの病巣をかかえ、幼い子供達へ少しでも思い出を残そうとマウイ島へ行くと聞き、スゴイなーと思ったのは去年の夏のことだった。ほぼ毎日アップされる彼のブログからは、大好きだった海をじっと眺める様子がうかがえた。最後のブログは亡くなる一週間前。ちょっと不思議な言葉が残されていた。「電波OKのところを見つけました。ちょいと離れていますが、、、。とにかく、これでバッチ・グーです」。新しもの好きで、誰よりも早くi Phone を手に入れていた彼のこと、きっと彼岸でも素敵なWiFi環境を見つけたに違いない。まれに見るオプティミストよ、さようなら。
 猛暑の中、ハンス・コパー展を見るために東京へ行った。ルーシー・リー初期のカップ裏面に並んだふたつのモノグラムを見て以来、あの大きな目をした男が気になって仕方がなかったからだ。よく知られるように、1950年代のコパーはリーにとってなくてはならない存在だった。しかし、リーに比べると日本でのコパーの知名度は低い。
猛暑の中、ハンス・コパー展を見るために東京へ行った。ルーシー・リー初期のカップ裏面に並んだふたつのモノグラムを見て以来、あの大きな目をした男が気になって仕方がなかったからだ。よく知られるように、1950年代のコパーはリーにとってなくてはならない存在だった。しかし、リーに比べると日本でのコパーの知名度は低い。