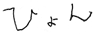「音のある休日」 #10
November 18th, 2009
 クァンティック・アンド・ヒズ・コンボ・バルバロ / トラディション・イン・トランジション
クァンティック・アンド・ヒズ・コンボ・バルバロ / トラディション・イン・トランジション
イギリスから南米コロンビアに移り住んだクァンティックことウィル・ホランドの音楽を、一言で表すのは難しい。 様々なラテン・リズムを核に、アフリカ、アラブ、インドなどの音楽をミックスし、ファンキーでサイケデリックに料理しているからだ。いずれの曲も、その「洗練されすぎなさ」が魅力のダンス・ミュ−ジックである。
ワールド・ミュージックと呼ばれる音楽は、もちろん国家別に存在するのではない。もっとローカルな色合いを持つものだ。互いに影響を受けながら変化してゆく様子こそスリリングなのだ。他者を拒否するのではなく、おのおのが持っているリズムを面白がることは、音楽の世界では大昔から当たり前。ゴキゲンに悲しい熱帯のグルーヴだ。(西日本新聞10月18日朝刊)
「何ぞテキトーな牛の絵ありまへんか」
November 12th, 2009
『小早川家の秋』は、小津安二郎の映画の中では最後から数えて2番目の作品になる。様々な事情から、所属していた松竹ではなく、宝塚(東宝)で撮られている。そのためか、いつもとは違った気配がある。まずいつもの東京弁ではなく、関西弁、京都弁というだけで、なんだか勝手が違う。その上に、あの小津独特の抑制された様式美が、松竹以外の俳優の参加で少なからず攪乱されている。なにより中村雁治郎演じる老人の酔狂振りである。しかし、そこは歌舞伎役者、京都の粋を感じさせてくれるから楽しむことが出来る。問題は、映画冒頭と途中にだけ顔を出す森繁久彌のバタ臭い関西人振りである。鉄工所の社長である森繁が原節子演じる画廊勤めの未亡人に、「何ぞテキトーな牛の絵ありまへんか」と露骨に交際を迫るシーン。普段アートなどには無縁な町工場のオッサンのえげつない感じが出ていて、観る度にギョッとしてしまう。隣にいるのが加藤大介という、まるで「社長シリーズ」そのままの構図なのも皮肉だ。小津自身は達者すぎる役者はダメだったようで、ましてアドリブが得意という森繁久彌を自分の映画に出演させることにはかなりの抵抗感があったとのこと。でも、そんなことを承知の上で怪演技を披露するのは森繁ならではパフォーマンスだ。バーのカウンターで、あんなにつまらなさそうにピーナツを口に放り込む仕草は、もう誰にも真似できないだろう。
PENDLETON
November 10th, 2009
 冬が近くなるとチェックが着たくなる。ブラックウォッチや鮮やかなチェックもいいが、アメリカ中西部の農夫が着そうなボンヤリ柄のペンドルトン。できれば茶系アースカラーのユーズド、乾燥機でキュッと縮んだやつが欲しい。
冬が近くなるとチェックが着たくなる。ブラックウォッチや鮮やかなチェックもいいが、アメリカ中西部の農夫が着そうなボンヤリ柄のペンドルトン。できれば茶系アースカラーのユーズド、乾燥機でキュッと縮んだやつが欲しい。
ペンドルトンといえばネイティブ・アメリカン風のブランケットも有名だけれど、アレッと思ったのは60年代にビーチ・ボーイズが着ていたってことだ。ストライプの半袖シャツがトレードマークだと思っていたのだが、CDを見ると、確かにサーフボード片手に全員がブルーのペンドルトン姿である。別名”ペンドルトンズ”とも呼ばれていたという話もあるくらいだが、企業タイアップだったのかもしれない。田舎っぽいシャツが、当時のカルチャーと一緒になって最新ファッションに変わったってことか。
つい先日、街ですれ違った女性。白のペインターパンツにボーイズサイズのペンドルトン。思わず振り返りたいほどキュートだった。その後、organによく来ていただく小柄なお洒落さんも同じペンドルトンを着ていたことが判明。きっと、どこかのショップがサイズを今風にアレンジして別注で作ったにちがいない。あの大きなフラップ付きのポケットや、とんがった襟はまちがいない。
それにしても、チェックというのは世界中に点在している柄。スコットランドはもちろん、アジアにも、アフリカにもある普遍的なモチーフのようである。時にはザズーやパンクスみたいにアンチな人たちのシンボルになってしまうところも面白い。難点はただひとつ、すぐに飽きてしまい、また別のチェックに目移りしてしまうところと、着るとやっぱり似合わないところか。それでも、夏にはやっぱりマドラス・チェックを探してしまう。結局、季節に関係なくチェックが好きなだけの話なのだ。
唐津くんち
November 5th, 2009
 一昨日、パリから戻ったばかりのユカリンと一緒に、唐津くんちへ行ってきた。つい10日ほど前はマレあたりを一緒に歩いていたのに、日を置かず今度は唐津で再会。活動的な人なのだ。彼女の友人である老舗呉服屋の若旦那のお誘いで、4軒ものお宅をハシゴしてしまい、美味しい手料理を堪能した。
一昨日、パリから戻ったばかりのユカリンと一緒に、唐津くんちへ行ってきた。つい10日ほど前はマレあたりを一緒に歩いていたのに、日を置かず今度は唐津で再会。活動的な人なのだ。彼女の友人である老舗呉服屋の若旦那のお誘いで、4軒ものお宅をハシゴしてしまい、美味しい手料理を堪能した。
まずは昼からS邸でアラの刺身。唐津くんちといえばコレだ。今まで「アラのようなもの」しか食べてなかったことが判明、その堂々とした本物の魚振りに驚いた。味は脂がのっているのにさっぱりしている。他にも生きのいい魚が一杯。シャンペンとワインで昼間からすっかりいい気分だ。続いては川島豆腐へ。いつもの入り口ではなく、豆腐工場を抜けて裏にある秘密の会場へ。ここではローストしたアグー豚をいただいた。沖縄産らしく、中国原種との交配種とのこと。優しい甘みがクセになりそうな味である。そして大将が丹精した唐津限定の新米のおにぎり。塩も付いてないのに、一粒一粒が甘く香ばしい。あまりの旨さにぬか漬けと一緒に2個パク付く。ここで、一旦ホテルのチェックインを口実に、シャワーを浴びて小休止。なにしろ、お腹いっぱいなのである。
それにしても、豊穣の祭りらしく、皆さんよく食べて飲むし、よく喋り冗談も達者だ。博多の山笠とは明らかに違う。次のお宅へ伺う途中でようやく遭遇した曳き山も、勇壮というのではなく、子どもやお年寄りが一緒になってソロリソロリと練り歩くのだ。そのお宅では、家庭料理をいただき、何人かの福岡の知り合いにも会い、ビックリ。みんなが誰かのつながりで偶然集うのも嬉しいことだ。唐津くんち独特のかけ声「エンヤ」が、なんだか「(コレも何かの)縁や!」に聞こえてしまう。最後は洋々閣へタクシーで乗り込み、泊まり客も一緒に座敷で車座。巨大なアラの煮付けが旨過ぎる。隆太窯の太亀さんもすっかり出来上がっているようだ。
唐津くんちは正月よりも盛大だとのこと。そういえば、伺ったお宅ではどこも最後にかならず「来年もぜひいらしてください」との言葉が添えられる。あるおじいさんは「良い年を!」とまでおっしゃった。美しい晩秋の一日が足早に暮れていった。
素足のサイズ計測
November 1st, 2009
 オテル・ドヴィルの前にあるBHVでユカリンと待ち合わせて、マレの方角へブラブラ散歩していたらANATOMICAの店の前を通りかかった。80年代半ば初めて訪れたパリではフレンチアイビーの牙城だったHEMISPHEREへ行くのが目的のひとつだった。そのオーナーだったピエール・フルニエ氏が90年代にビルケンシュトックをメインにしたショップを開いたことは知っていたし、確かその後一度は訪れたはずなのだが・・・。
オテル・ドヴィルの前にあるBHVでユカリンと待ち合わせて、マレの方角へブラブラ散歩していたらANATOMICAの店の前を通りかかった。80年代半ば初めて訪れたパリではフレンチアイビーの牙城だったHEMISPHEREへ行くのが目的のひとつだった。そのオーナーだったピエール・フルニエ氏が90年代にビルケンシュトックをメインにしたショップを開いたことは知っていたし、確かその後一度は訪れたはずなのだが・・・。
イソイソと店内に入ると、エレファントスツールのオリジナルが置いてある。先日Pucesで見かけたものの、つい買い逃してしまったのと同じジェット・ブラックで、いい感じに色あせている。店内はさほど広くもなく、日本のワラジや古いかすりが置いてあったりしてなかなか興味深い。しかし、目は壁に引っかけてあるオールデンのダーティーバックスに釘付けだ。サイズの有無を尋ねると、ピエール氏が地下のカーヴにストックを調べに行ってくれたが、あいにく9.5インチしかないらしく僕には大きすぎる。ブラウンなら小さいサイズがあるのだが、さて・・・、と逡巡していたら、「足のサイズを測りましょうか」とのお誘い。レッドウィング社の古いフィッティング・ゲージでムッシューじきじきに計測してもらうのもいい経験だと思って靴を脱いだ。
僕は、「多分8.5のDかEだと思う」といったのだが、結果は8のDらしい。ところが、ムッシューは「靴下を脱げ」という。確かにちょっと厚めのソックスを穿いてはいたが、それにしても慎重な人である。気恥ずかしかったが、いわれるがままに冷たい金属のゲージに足を置くと、ムッシューはその細い指で僕の素足を台座にキチンと固定し、おもむろに「まちがいない、お前は8のDである」と宣言した。昔の僕なら、ここで観念してブラウンを購入したのだろうが、今は違う。やはり、ダーティーバックスが欲しいので、と断った。そのかわり、濃いブラウンのシェットランド・セーターをいただくことにして店を後にした。
Villa Vanille
October 29th, 2009
 マラケシュのホテルはとても居心地が良かった(見つけてくれたウチの奥さんに感謝)。若いフランス人夫婦が経営するゲストハウスなのだが、広めの敷地にはプールが2つあり、サボテンやオリ−ブの木の間をラバや山羊が放し飼いされていたりする。点在する数軒のコテージのモロッコらしい内装や小物も、オーナー2人のセンスが表れているようで、ゴージャスとは違ったリラックス感がとてもいい。
マラケシュのホテルはとても居心地が良かった(見つけてくれたウチの奥さんに感謝)。若いフランス人夫婦が経営するゲストハウスなのだが、広めの敷地にはプールが2つあり、サボテンやオリ−ブの木の間をラバや山羊が放し飼いされていたりする。点在する数軒のコテージのモロッコらしい内装や小物も、オーナー2人のセンスが表れているようで、ゴージャスとは違ったリラックス感がとてもいい。
着いた日のランチは、僕らのコテージのテラスでNさん達とタジンをいただいた。チキンと野菜がサフランでトップリと煮込んであって、旅の疲れが吹っ飛ぶような美味しさだった。母屋は古い建物で、居間や食堂、台所などが自由に出入りできる。レセプションもなく、客は図書室やあずま屋など各々好きな所でくつろぐことができる。ただ、コテージには電話がないので、用事があるときは大きな台所を抜けて、オーナーであるフローレンスのいる部屋へ出向かなければならない。
暇に任せて庭をフラフラしているうちに、大きなうちわサボテンの赤い実が目に入った。たしか食べられるはずである。もちろん、その気はないのだが、好奇心も手伝いどんな固さかと触ってみることにした。棘はなく、細かな繊毛に覆われているようだ。そのまま、その場を立ち去ったのだが、なんだか指がチクチクする。見ると、親指と人差し指の先にびっしりと小さな棘が刺さっているのだ。細かい繊毛と思ったのが早とちりだった。1ミリにも満たないような棘だから、全部をうまく抜くことができない。無視しようと思っても、指をこすり合わせると明らかに小さな痛みが走ってしまう。
どうしたものかと思案しているとハッサンがやってきた。その旨を伝えると、チューインガムで取れるという。一枚噛むのももどかしく、まだベタベタしかけたガムをくっつけては離し、くっつけては離し、最後の一本を取るまで終始無言だった。気のせいか、しばらくはまだ一本くらい残ってるような気がしてならなかった。
Couleur Cafè
October 29th, 2009
 無事アギーユ・ドゥ・ミディ征服後、登りと同じロープーウエーで一段下の乗り換え地点まで下る。ここまで来ると、少し人間界に近い気がする。見ると、少し離れた場所に山小屋みたいなものがある。ドイツ語ではヒュッテというのだろうがBARという文字も見える。吸い寄せられるように小屋の中へおじゃますると、髭を生やしたおじさんが退屈そうに新聞を読んでいる。ちょっとしたみやげ物がテーブルに並んでいるのだが、床には大きなリュックとヘルメットが置いてある。頂上を目指してちゃんと自分の足で登る人のための中継地なのだろう。メニューを見ると、赤ワインがある。暖かいヴァンショーをお願いしたが、あいにくやってない。しかたなく、ボルドーのグラスをお願いし、勘定をするためにカウンターの近くへ行くと音楽が流れているのに気がついた。低域がカットされた小さなラジオ独特の痩せた響きだが、どこかで聴いたようなメロディーだ。ちょっとラテンっぽい。そのままテラスへ向かいかけた瞬間「クーラーカフェ・・・」という歌詞が耳に飛び込んできた。ゲンさんである!こんな場所でのゲンズブールとの遭遇に、思わず膝を打った。確かにここはアルプスとはいえフランスなのだから不思議ではないのかもしれないが、なにせクーラーカフェ、この場所にピッタリの語感ではないか。ひとり悦にはいり、ハミングなどしながら、しばしあたりをトレッキング気分でそーついた。でも、日本に戻って調べると「コーヒー色」とサブタイトルが付いている。自分の勘違いに寒けがした。
無事アギーユ・ドゥ・ミディ征服後、登りと同じロープーウエーで一段下の乗り換え地点まで下る。ここまで来ると、少し人間界に近い気がする。見ると、少し離れた場所に山小屋みたいなものがある。ドイツ語ではヒュッテというのだろうがBARという文字も見える。吸い寄せられるように小屋の中へおじゃますると、髭を生やしたおじさんが退屈そうに新聞を読んでいる。ちょっとしたみやげ物がテーブルに並んでいるのだが、床には大きなリュックとヘルメットが置いてある。頂上を目指してちゃんと自分の足で登る人のための中継地なのだろう。メニューを見ると、赤ワインがある。暖かいヴァンショーをお願いしたが、あいにくやってない。しかたなく、ボルドーのグラスをお願いし、勘定をするためにカウンターの近くへ行くと音楽が流れているのに気がついた。低域がカットされた小さなラジオ独特の痩せた響きだが、どこかで聴いたようなメロディーだ。ちょっとラテンっぽい。そのままテラスへ向かいかけた瞬間「クーラーカフェ・・・」という歌詞が耳に飛び込んできた。ゲンさんである!こんな場所でのゲンズブールとの遭遇に、思わず膝を打った。確かにここはアルプスとはいえフランスなのだから不思議ではないのかもしれないが、なにせクーラーカフェ、この場所にピッタリの語感ではないか。ひとり悦にはいり、ハミングなどしながら、しばしあたりをトレッキング気分でそーついた。でも、日本に戻って調べると「コーヒー色」とサブタイトルが付いている。自分の勘違いに寒けがした。
AIGUILLE du MIDI
October 28th, 2009
 シャルロット・ペリアンが手がけた施設レザルク2000を見たかったのだが、あいにくスキーシーズン直前でクローズしていたため代わりにモンブランへ行くことにした。ジュネーブからバスで2時間ほどで麓のシャモニーに着く。目の前は壁のように立ちはだかる山だ。頂上は見えない。これからロープーウエーに乗って、はるか雲上まで登るのかと思うと武者震いしそうだ。実は、帰国後に仲間と一緒に出す予定の同人誌”Yodel”のために、どうしても雄大な山の写真が欲しい。仕事の都合でひとあし先にモロッコから帰国したデザイナーのNさんから「山の写真、ヨロシク!」と言い渡されているのだ。
シャルロット・ペリアンが手がけた施設レザルク2000を見たかったのだが、あいにくスキーシーズン直前でクローズしていたため代わりにモンブランへ行くことにした。ジュネーブからバスで2時間ほどで麓のシャモニーに着く。目の前は壁のように立ちはだかる山だ。頂上は見えない。これからロープーウエーに乗って、はるか雲上まで登るのかと思うと武者震いしそうだ。実は、帰国後に仲間と一緒に出す予定の同人誌”Yodel”のために、どうしても雄大な山の写真が欲しい。仕事の都合でひとあし先にモロッコから帰国したデザイナーのNさんから「山の写真、ヨロシク!」と言い渡されているのだ。
一気に登ると高山病の危険があるらしい。さいわい、途中2000mくらいで一旦降りて別のロープーウエーに乗り換えるとのこと。おそらく上はかなりの寒さに違いない。この日のため防寒用にエヴァーウォームの下着を着込んでいるのだが、それにしても、もはや寒い。35度の砂漠から一気に零下の世界へやって来たわけで、身体が順応していない。回りもほとんどの人がそれなりの格好をしている中で、異彩を放っているのがバスでひっきりなしに喋っていた4人の謎の中国人だ。全員ワイシャツに薄いグレーの背広姿でマフラーもなし、という軽装は、傍目にも大丈夫かな、と思ってしまう。そんなことにはお構いなしに、ほとんど垂直かと思われるロープーウエーに乗った僕らは、またたく間に標高3842m、終点のアギーユ・ドゥ・ミィディと呼ばれる展望台に運び上げられた。
それから先のことは筆舌に尽くしがたいほどクールだった。つまり、寒さを通り越した無我の境地だったわけだ。写真を撮ろうにも、強風のせいか足と指先の血流がストップしていることが歴然で、なにごとも思うに任せない。めったやたらにシャッターを切る。そんな中でタバコを一服したら(風か気圧なのか、なかなかライターが付かないのだが)、今まで味わったことがないほど旨かった。
しかし、15分が限界だった。暖かいカフェテリアに逃げ込み、ホットチョコレートを飲んでいると、くだんの中国人達もやって来た。でも、ポケットに手を突っ込んだだけで、寒そうだけど案外平気そうだ。しばらくすると、彼らは何も飲まず、又そそくさと極寒の世界へ消えていった。何か使命でもあったのだろうか?クールだ。
ハッサン
October 25th, 2009
 旅の醍醐味のひとつは人との出会いなのだが、今回ほど様々な人とソデスリアエタことはないと思う。そのほとんどは、パリに住むユカリンのおかげなのだが、彼女が紹介してくれたのがモロッコで会ったハッサンだ。マラケシュにあるスークの中でじゅうたん屋を営む彼は、法外な値段をふっかけるのが当たり前のスークで唯一信頼できるディーラーだとのこと。東京で行われたモロッコのクラフト展のために来日したこともあるという彼のコレクションは、確かに見応えがあり、様々なキリムの中でもなるだけシンプルなものを何枚かいただくことになった。正直なところ、あの狂騒のフナ広場をやっと抜け出て、温厚な顔の彼に出会ったとたん、なんだかホッとした気持ちになったものだ。
旅の醍醐味のひとつは人との出会いなのだが、今回ほど様々な人とソデスリアエタことはないと思う。そのほとんどは、パリに住むユカリンのおかげなのだが、彼女が紹介してくれたのがモロッコで会ったハッサンだ。マラケシュにあるスークの中でじゅうたん屋を営む彼は、法外な値段をふっかけるのが当たり前のスークで唯一信頼できるディーラーだとのこと。東京で行われたモロッコのクラフト展のために来日したこともあるという彼のコレクションは、確かに見応えがあり、様々なキリムの中でもなるだけシンプルなものを何枚かいただくことになった。正直なところ、あの狂騒のフナ広場をやっと抜け出て、温厚な顔の彼に出会ったとたん、なんだかホッとした気持ちになったものだ。
ハッサンという名前を聞いてすぐに頭をよぎったのはアリ・ハッサンというスーダンのミュージシャンだった。ナイルの上流、ヌビア地方のダンス・ミュージックのマエストロで、キューバ音楽とミックスした強力なグルーヴは頭がクラクラするほどかっこよく、僕は一時中毒になったことがある。アラブ圏でハッサンという名前は多分ポピュラーなのだろうと思いながらもハッサンに尋ねると、なんと彼もアリ・ハッサンが大好きらしく、彼との距離がグッと縮まったような気がした。ついでに、グナワ・ミュージックはどうか、と聞いたら、もちろん好きだ、お前にアリ・ハッサンとグナワのベストなCDを帰る前にプレゼントする、と約束してくれた(結局この約束は守られなかったが・・・、インシャラーである)。実際、こんな時には音楽は便利な共通語になってくれる。
3日目は朝からハッサンと一緒にアトラス山脈へ車で一日ツアー。マラケシュを出て信号なしでバカみたいに真っ直ぐな道をひたすら走ると、突然茶色をした山岳地帯へさしかかる。ガードレールもない曲がりくねった道を、かなりのスピードで上るエアコンの壊れたワゴン車は、これでも上等の方なのだ。気がつくと標高1500m、そこだけ緑に覆われた谷間のウリカ村へ到着。リンゴの産地らしくレストランで食べた地元料理タジンも美味しかった。そしてハッサンの友人宅でミント・ティーをいただき休憩。この人の名前もハッサンらしい。ハッサンだらけだ。それに、ミント・ティーだらけ。何処へ行っても、まずはミント・ティー。甘く香しいミントの香りと、ハッサンのちょっと汗臭いワイシャツの匂いがなつかしい。
une petite maison
October 24th, 2009
 ジュネーブのホテルを朝9時に出て、左に葡萄畑、右にレマン湖畔というスイスならではの眺望を楽しみながら列車に揺られること小一時間、小さな町ヴェヴェイに到着。駅で尋ねると、湖畔沿いに歩いて20分くらい、迷うことなく行けることが分かった。この様子だと、約束の時間にはたどり着けそうだ。なにしろ週に一日、水曜日が原則なのに、事前のメールでなんとか金曜の見学を許されたのだから遅れるわけにはゆかない。しばらく歩くと、ネスレ本社ビルを過ぎたあたり、国道と湖に挟まれるような三角地に目的の「小さな家」が目に入る。アルミニウムの外壁に覆われた細長い建物は、なんだかワゴンみたいだ。
ジュネーブのホテルを朝9時に出て、左に葡萄畑、右にレマン湖畔というスイスならではの眺望を楽しみながら列車に揺られること小一時間、小さな町ヴェヴェイに到着。駅で尋ねると、湖畔沿いに歩いて20分くらい、迷うことなく行けることが分かった。この様子だと、約束の時間にはたどり着けそうだ。なにしろ週に一日、水曜日が原則なのに、事前のメールでなんとか金曜の見学を許されたのだから遅れるわけにはゆかない。しばらく歩くと、ネスレ本社ビルを過ぎたあたり、国道と湖に挟まれるような三角地に目的の「小さな家」が目に入る。アルミニウムの外壁に覆われた細長い建物は、なんだかワゴンみたいだ。
身の丈ほどの茶色いドアを開けると、室内に暖気が感じられる。遠来の客としてはうれしい限り。係の女性ジャネッテさんが笑顔で迎え入れてくれると、挨拶もソコソコに室内を歩き回る。なんと幸せな時間だろう。特徴的な11mの横に長いガラス窓からはキラキラと陽光が湖面に反射し、彼方にアルプスが遠望できる。ここで、コルビュジエは母との時間をゆっくりと過ごしたに違いない。朝日を取り入れる高窓、仕切をスライドさせるとゲストのためのベッド、兄と2人で滞在するための秘密の小部屋(?)、愛犬のためののぞき窓、屋上緑化。随所に細かな工夫が凝らされて、ジャネッテさんの説明がひとつひとつの謎を解いてくれるようだ。家というものは、必ずしも広ければいいというわけではない。狭小であっても、日が良く当たる庭があって、必要にして充分な設備さえあればいい。
ほぼすべてがオリジナルの状態というのも嬉しかった。しかも、どこを触れてもOK。もちろん椅子に座ることも許されている。で、置いてあるLCシリーズの椅子もオリジナルですか、と質問したところ、2脚のうちの1脚だけがそうだとのこと。言われてみれば、確かに細部に違いがある。すると、ジャネッテさんが持ってみろというジェスチァーをした。持ち上げると、軽い。イームズのLCWやDCWもそうだけど、オリジナルといわれるものはリプロダクトに比べると、かなりの度合いで重量が軽い場合が多い。それはちょっとした感動ですらある。
実を言えば、僕はかねてからコルビュジエについて回る「巨匠」という字が苦手だった。だからこそ、この「小さな家」に来て良かったと思う。快適さとは、ある種の軽さなのかもしれない。
 クァンティック・アンド・ヒズ・コンボ・バルバロ / トラディション・イン・トランジション
クァンティック・アンド・ヒズ・コンボ・バルバロ / トラディション・イン・トランジション