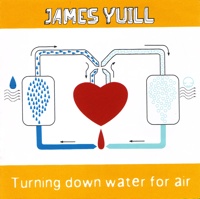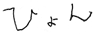「音のある休日」#9
October 7th, 2009
グレゴリー・アンド・ザ・ホーク / イン・ユア・ドリームス
 「タフでいることにはもうヘトヘトなの・・・」。訥々(とつとつ)とした生ギターをバックに、舌っ足らずのチャーミングな声が耳元でささやく。歌っているのはニューヨーク出身の女性シンガー&ソングライター、メレデス・ゴドルー。まるでアメリカのインディペンデント映画の主人公のように、リアルだ。
「タフでいることにはもうヘトヘトなの・・・」。訥々(とつとつ)とした生ギターをバックに、舌っ足らずのチャーミングな声が耳元でささやく。歌っているのはニューヨーク出身の女性シンガー&ソングライター、メレデス・ゴドルー。まるでアメリカのインディペンデント映画の主人公のように、リアルだ。
小さなコーヒーハウスで歌っていた彼女がユニット名義の自主製作でCDデビューしたのは、4年ほど前。その中の1曲が”MySpace”と呼ばれるインターネットのコミュニティ・サイトで公開され話題を呼んだ。その後、草の根のように静かな展開を広げ、日本でもCDが発売されることになる。変革の中、ささやかな日常を歌う姿に、今のアメリカが透けて見えるようだ。(西日本新聞10月4日朝刊)
久生十蘭の「従軍日記」
October 2nd, 2009
 久生十蘭の「従軍日記」を読んでみた。戦意高揚の記事を書く人気作家としての彼は、インドネシアで酒と麻雀と慰安婦に溺れる苦渋の日々を送り、ニューギニアの前線ではアメリカ軍の爆撃の恐怖を味わうという経験をすることになる。アブナイ言葉をフランス語に代えながらつづられる細かな日々の記録は、そのまま当時の知識人の有り様を見るようだ。太平洋の広大な地域に展開した日本の不毛な戦争に、彼自身は案外コミットしていたことをうかがい知ることができる。
久生十蘭の「従軍日記」を読んでみた。戦意高揚の記事を書く人気作家としての彼は、インドネシアで酒と麻雀と慰安婦に溺れる苦渋の日々を送り、ニューギニアの前線ではアメリカ軍の爆撃の恐怖を味わうという経験をすることになる。アブナイ言葉をフランス語に代えながらつづられる細かな日々の記録は、そのまま当時の知識人の有り様を見るようだ。太平洋の広大な地域に展開した日本の不毛な戦争に、彼自身は案外コミットしていたことをうかがい知ることができる。
20年ほど前、バリ島の隣のロンボクという島へ行ったことがある。ある朝、ホテルの前のビーチから「ギリ・アイル」と呼ばれる、さらに小さな島へカヌーで渡ってみることにした。1時間ほど波間を揺られ、ようやく視界に入ったその島の隣にちっぽけな岩だらけの小島があった。船頭が、頂上の黒い物体を指さしながら、旧日本軍の砲台だと教えてくれた。戦略的にはさして重要とも思われない孤島にポツンと置き忘れられた大砲。目の覚めるような青空をバックにした、この天国のような小島に配属させられた兵隊は、毎日一体何を考えて過ごしたのだろう、と不思議な気持ちになったことを覚えている。
僕は、いわゆるジュウラニアンではなく多くの作品を読んだわけでもない。本の表紙に写る写真が、幼い頃見た父の軍装姿とほぼ同じポーズ、表情だったことに興味を惹かれたのだろう。長靴を履き、軍刀を杖のようにして虚空を見つめるポートレイトは、さながら当時の日本男児のアイコンのようだ。
カナダに興味がある。
September 27th, 2009
 ラサ(Lhasa)という女性シンガー&ソングライターの同名タイトルCDを聴いている。世の悲しみを一身に背負ったかのような声とメロディに、ふと同じカナダ出身のレナード・コーエンを思い浮かべてみる。ついでに、リチャード・マニュエルやニール・ヤング、ジョニ・ミッチエルも。いづれも、ベトナム戦争の時代に、アメリカに対して批評的立場を取ったカナダ人なのだが、デビュー時はてっきりアメリカ人だと思っていた。一見、アメリカと区別が付きにくいカナダだが、実際は随分様子が違うようだ。歴史的には、両国ともイギリスの支配から独立している。カナダ東部大西洋岸は元来フランス領だった。それをイギリスが破ったわけだが、直後にそのイギリス軍にいたジョージ・ワシントン等が、皮肉にもイギリスを相手に戦争をしかけ、アメリカが独立を果たしている。その際、カナダでのフランス軍はインディアンと共闘を組んでいたということを知った。戦略的理由だったのかもしれないが、先日のヴェトナムでの話と合わせて、ネイティヴへの配慮を感じさせるフランスを想像した。そういえば、フランス系カナダ人のミュージシャンを意識したのはルイス・フューレイが最初だった。あの強烈な個性は、ちょうど聴き始めたばかりのセルジュ・ゲンズブールと一緒くたになって、時代遅れのダンディズムへのあこがれを加速させた。そんなカナダ人で2004年に「LANDAU」というアルバムを出したのがMantler。ウーリッツァーの侘びたエレピ音をバックに、ロバート・ワイアットを幼くしたような痛切な声で甘美なメロディを紡ぎ出すおじさんである。話が散漫になったが、要はカナダに興味がある、ということだ。いつか行ってみたいとも思う。でも、何処へ行けばいいのか、まったく焦点が定まらない。まさか、今さらアウトドアに目覚めそうにはないが、モノ探しではない旅がしてみたい。秋なのだ。
ラサ(Lhasa)という女性シンガー&ソングライターの同名タイトルCDを聴いている。世の悲しみを一身に背負ったかのような声とメロディに、ふと同じカナダ出身のレナード・コーエンを思い浮かべてみる。ついでに、リチャード・マニュエルやニール・ヤング、ジョニ・ミッチエルも。いづれも、ベトナム戦争の時代に、アメリカに対して批評的立場を取ったカナダ人なのだが、デビュー時はてっきりアメリカ人だと思っていた。一見、アメリカと区別が付きにくいカナダだが、実際は随分様子が違うようだ。歴史的には、両国ともイギリスの支配から独立している。カナダ東部大西洋岸は元来フランス領だった。それをイギリスが破ったわけだが、直後にそのイギリス軍にいたジョージ・ワシントン等が、皮肉にもイギリスを相手に戦争をしかけ、アメリカが独立を果たしている。その際、カナダでのフランス軍はインディアンと共闘を組んでいたということを知った。戦略的理由だったのかもしれないが、先日のヴェトナムでの話と合わせて、ネイティヴへの配慮を感じさせるフランスを想像した。そういえば、フランス系カナダ人のミュージシャンを意識したのはルイス・フューレイが最初だった。あの強烈な個性は、ちょうど聴き始めたばかりのセルジュ・ゲンズブールと一緒くたになって、時代遅れのダンディズムへのあこがれを加速させた。そんなカナダ人で2004年に「LANDAU」というアルバムを出したのがMantler。ウーリッツァーの侘びたエレピ音をバックに、ロバート・ワイアットを幼くしたような痛切な声で甘美なメロディを紡ぎ出すおじさんである。話が散漫になったが、要はカナダに興味がある、ということだ。いつか行ってみたいとも思う。でも、何処へ行けばいいのか、まったく焦点が定まらない。まさか、今さらアウトドアに目覚めそうにはないが、モノ探しではない旅がしてみたい。秋なのだ。
「音のある休日」#8
September 18th, 2009
 ハウシュカ / スノーフレイクス・アンド・カーレックス
ハウシュカ / スノーフレイクス・アンド・カーレックス
1890年代にエリック・サティが提唱した「家具の音楽」は、常識を覆す革命だった。なんと、史上初の「無視することもできる音楽」が登場したのである。といっても、ここに紹介するドイツ出身、ハウシュカの存在は無視できそうにないのだけれど・・・。
日々量産される音の洪水の中、 「押しつけがましさがなく、(家具の様に)そこにあるだけの音楽」は、その後「環境音楽」とも呼ばれことになる。ポロン、ポロンと繰り返される印象的なピアノのフレーズは、短かかった夏の終わりによく似合う。そんな、知的で実験的なハウシュカのライブにもうすぐ福岡で出会える。単なる「癒し」を超えた濃密な時間を期待している。この最新アルバムを聴いて、しっかり予習しておこう。
(西日本新聞9月20日朝刊)
Au Revoir Simone
September 11th, 2009
 オ・ルヴォワール・シモーヌというガーリー・ユニットのCDをアメリカから取り寄せてorganで販売していたのは2年ほど前。毎日のように聴いていたあの頃に来福してくれていたら、などと思いつつライブ会場へ向かう。小さな会場は、案の定スタンディングで、隅の方に申し訳程度のイスが数脚。優先席とばかり、小さなすきまを見つけて座らせてもらう。缶ビールをチビチビやりながら、知人でもある田中ゴロー君のユニット「lem」の演奏に耳を傾けた。CDで聴くよりずっと骨太の音が気持ち良い。二組目のバンドがラウド系だったのを潮時に、近所の焼鳥屋へエスケイプ、彼女たちの出番とおぼしき時間になりそそくさと会場へ戻ると、待つほどのこともなく演奏が始まった。ドラムマシーンをバックに、ミニサイズのシンセをピコピコ操る三人娘がそこにいた。聞き慣れた曲を耳にし、おもむろにステージ近くへ移動。イイ。耽溺していた80年代の「ヘタウマ」といわれたミューズ達が、走馬燈のように脳裏を駆けめぐる。アンテナ、アンナ・ドミノ、ミカド、そしてベントゥーラ。待てよ、彼女たちはブルックリン出身だったはず。そういえばローチェスっぽくもあるし、いにしえのガーリー・ガレージ系シャングリラスのソフトヴァージョンといえなくもない。なにより決定的なのは、向かって左端、ブルーネットの娘の歌声である。なんと、スラップ・ハッピー時代のダグマー・クラウゼの遺伝子「明るい絶望感」を持っているではないか!それにしても、3人ともスキニー過ぎる。目の毒だ。おかげで最後まで立ちっぱなしの有様だった。
オ・ルヴォワール・シモーヌというガーリー・ユニットのCDをアメリカから取り寄せてorganで販売していたのは2年ほど前。毎日のように聴いていたあの頃に来福してくれていたら、などと思いつつライブ会場へ向かう。小さな会場は、案の定スタンディングで、隅の方に申し訳程度のイスが数脚。優先席とばかり、小さなすきまを見つけて座らせてもらう。缶ビールをチビチビやりながら、知人でもある田中ゴロー君のユニット「lem」の演奏に耳を傾けた。CDで聴くよりずっと骨太の音が気持ち良い。二組目のバンドがラウド系だったのを潮時に、近所の焼鳥屋へエスケイプ、彼女たちの出番とおぼしき時間になりそそくさと会場へ戻ると、待つほどのこともなく演奏が始まった。ドラムマシーンをバックに、ミニサイズのシンセをピコピコ操る三人娘がそこにいた。聞き慣れた曲を耳にし、おもむろにステージ近くへ移動。イイ。耽溺していた80年代の「ヘタウマ」といわれたミューズ達が、走馬燈のように脳裏を駆けめぐる。アンテナ、アンナ・ドミノ、ミカド、そしてベントゥーラ。待てよ、彼女たちはブルックリン出身だったはず。そういえばローチェスっぽくもあるし、いにしえのガーリー・ガレージ系シャングリラスのソフトヴァージョンといえなくもない。なにより決定的なのは、向かって左端、ブルーネットの娘の歌声である。なんと、スラップ・ハッピー時代のダグマー・クラウゼの遺伝子「明るい絶望感」を持っているではないか!それにしても、3人ともスキニー過ぎる。目の毒だ。おかげで最後まで立ちっぱなしの有様だった。
空手黒帯有段者Yohji
September 10th, 2009
 街でばったりROVAのOBに出会い、ひとしきり昔話。彼がROVAに通っていたのは9年ほど前になるだろうか、女子率が高い生徒の中にあって、なんとスカート状のものを穿いたりと、コム・デ・ギャルソン顔負けの先鋭的なお洒落をしていたのだが、今では結婚をし、ビジネス・スーツ姿である。そんな彼から、ちょっと気になる話を聞いた。「ヨウジ・ヤマモト」の経営が危ぶまれている、とのこと。ま、変遷が激しいモード業界、何が起こっても不思議はないのだが。
街でばったりROVAのOBに出会い、ひとしきり昔話。彼がROVAに通っていたのは9年ほど前になるだろうか、女子率が高い生徒の中にあって、なんとスカート状のものを穿いたりと、コム・デ・ギャルソン顔負けの先鋭的なお洒落をしていたのだが、今では結婚をし、ビジネス・スーツ姿である。そんな彼から、ちょっと気になる話を聞いた。「ヨウジ・ヤマモト」の経営が危ぶまれている、とのこと。ま、変遷が激しいモード業界、何が起こっても不思議はないのだが。
随分前、FM番組のために山本耀司へインタヴューしたことがあった。鈴木慶一プロデュースでアルバムを出し、福岡にライブのためにやって来たときだった。幸運にも、行きつけのバーのカウンターに腰掛けて、いろいろな話を伺う機会を得た。彼がデザインした服も好きだったけど、たまたま立ち読みした雑誌での発言がすこぶる刺激的だったし、なによりその2、3年前に見たヴィム・ヴェンダース監督映画「都市とモードのビデオノート」での立ち居振る舞いにノックアウトされた身なればこそ、極度に緊張していた。
開口一番、当たり障りのない質問をするしかなかった。「福岡へはよくいらっしゃるのですか?」と。彼の答えは意外なものだった。「別れた女房が北九州出身なので、以前、小倉へはよく来てたんですが、福岡は滅多に来ないです」。なんというのか、初対面の挨拶にしてはフランク過ぎる。いや、ラディカルでさえある。でも、おかげで随分緊張が解けた気もした。それからかれこれ1時間ほど、服や音楽の話をした。柔らかだが核心を突いた話しぶりに聞き惚れてしまい、何を喋ったのかよく覚えていない。でも、彼がいった言葉のいくつかは鮮明に記憶している。「ナチスに追われる東欧の難民が着ていた服に嫉妬する」や、「アイデンティティなんか、いらない」などなど、「デラシネ」っぽいプレゼンスだ。リアルだったのは、「一番嫌いなのは、洋服に『お』を付けること」といっていたこと。確かに、「お洋服」とは笑止である。さて、空手黒帯有段者Yohji、これから何処へ行く。
USネービーのセーラーズ・ハット
September 8th, 2009
 夏の終わりに、かぶり物を買った。USネービーのセーラーズ・ハットで、レプリカだが良くできている。先週、今泉にある店「NAVY」で見つけ、欲しかったのだが辛抱した。何故かといえば、確かオリジナルの白を持っていたからである。ところが何処にあるのか判然としない。こういうときには奥さんに聞くのが一番。すると「随分前、車の中で見かけた」との答え。早速駐車場まで行き、車を物色すると案の定あった。ちょっと黄ばんでいるが、洗濯すればまだまだイケそうだ。そういえば中学生時分、「ホイホイ・ミュージックスクール」というテレビ番組のプレゼントに応募して、これに似た帽子をゲットしたことがあった。でも、ペナペナの生地の粗悪品で、被ってみたが全然似合わず、がっかりした覚えがある。ポパイみたいにツバを立てて被ったのがいけなかったようだ。その後しばらくして、ツバを下ろし、目深に被ると自分の不格好な頭が隠れて、案外具合が良いことを発見して、どこかの放出品屋で見つけたもの。しかし、この、オリジナルにあり得べくもない黒にも惹かれる。ここは、細部にこだわり別ヴァージョンを模索する日本のアパレルの力量に敬意を表して購入した。「CORONA」というマイナーなメーカー名が泣ける。
夏の終わりに、かぶり物を買った。USネービーのセーラーズ・ハットで、レプリカだが良くできている。先週、今泉にある店「NAVY」で見つけ、欲しかったのだが辛抱した。何故かといえば、確かオリジナルの白を持っていたからである。ところが何処にあるのか判然としない。こういうときには奥さんに聞くのが一番。すると「随分前、車の中で見かけた」との答え。早速駐車場まで行き、車を物色すると案の定あった。ちょっと黄ばんでいるが、洗濯すればまだまだイケそうだ。そういえば中学生時分、「ホイホイ・ミュージックスクール」というテレビ番組のプレゼントに応募して、これに似た帽子をゲットしたことがあった。でも、ペナペナの生地の粗悪品で、被ってみたが全然似合わず、がっかりした覚えがある。ポパイみたいにツバを立てて被ったのがいけなかったようだ。その後しばらくして、ツバを下ろし、目深に被ると自分の不格好な頭が隠れて、案外具合が良いことを発見して、どこかの放出品屋で見つけたもの。しかし、この、オリジナルにあり得べくもない黒にも惹かれる。ここは、細部にこだわり別ヴァージョンを模索する日本のアパレルの力量に敬意を表して購入した。「CORONA」というマイナーなメーカー名が泣ける。
「音のある休日」#7
September 6th, 2009
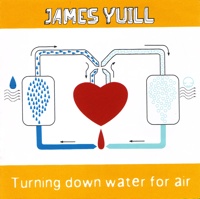 James Yuill / Turning down water for air
James Yuill / Turning down water for air
久しぶりに「シンガー・ソングライター」という言葉が浮かんだ。アコースティックとエレクトロニクスが気持ちよく調和したサウンドと、イギリスならではの愛すべきメロディー。なんだか名前「ユイル」が「ユルイ」に思えてしまうほど優しい歌声に、思わず耳をそばだてた。
インターネットの動画サイトを検索すると、観客を前にして生ギターを背中にしょって、いくつものコンピューター機材を操る彼の姿を見ることができる。社会的で内省的だった1960年代とは違い、ハイブリッドでしなやかなスタイルである。今のところ、輸入盤でしか聞けないのだが、ウェブ・ショップなどでは比較的容易に購入が可能だ。マイナーな音楽を楽しめる環境が嬉しい。
(西日本新聞9月6日朝刊)
「音のある休日」#6
August 29th, 2009
 マーシャ・クレラ / スピーク・ロウ
マーシャ・クレラ / スピーク・ロウ
ベルリン出身の女性マルチ・アーティスト待望のソロアルバム3作目。今回は、同じドイツ出身の作曲家クルト・ワイルなどの作品をカバーしたもの。
ワイルといえば1929年「三文オペラ」で有名になり、その後ブロードウェイに進出した音楽家。ドラマティックで感傷的なメロディが、今の時代、どんな風に料理されるか興味津々だった。
聞いてみると、シンプルなバンド・サウンドが意外にもマッチしている。限りなく少ない音で空間をデザインするスタイルは、やはりドイツならではのもの。マーシャの愁いを含んだ(といっても湿度ゼロの)ボーカルが、大衆音楽の古典に新らしい光を当てているかのようだ。
(西日本新聞8月23日朝刊)
キャンプ
August 28th, 2009
 『M*A*S*H』DVD特別編を観る。何度観ても、ドナルド・サザーランドの迷彩帽はダンディだし、例のエリオット・グールドがマティーニにオリーブを放り込むシーンには思わず膝を打ってしまう。サザーランドはカナダ出身、イギリスで舞台俳優としてデビュー、グールドはニューヨーク出身のユダヤ人でやはり舞台俳優。二人ともこの映画がきっかけで人気俳優となった。原作は朝鮮戦争を舞台にしたカートゥーンで、それに大胆&強烈なおふざけ感を加味したもの。1970年に公開され大ヒット、カンヌ映画祭でグランプリも取っている。当時はヴェトナム戦争まっただ中。一応朝鮮戦争を描いているのだが、見るうちにどうしてもヴェトナム戦争を連想してしまうところが監督ロバート・アルトマンの狙いだったようだ。それにしても、前述の2人が、軍隊という「真面目であるべき場」で演じる不真面目さがサイコーだ。それは、スーザン・ソンタグがいっている「キャンプな感覚」に近い。ソンタグは著書『反解釈』の中で「われわれは、不真面目なものについて真面目になることもできれば、真面目なものについて不真面目になることもできるのである」、といっている。ソンタグは又、対照的にポップ・アートについてこういっている、「キャンプと関係があるとしても、やはり平板で乾いており、真面目であり、究極においてニヒリスティックである」。これは、もちろんアンディ・ウォーホルを思い浮かべてもイイし”King Of Pop”と呼ばれることになった人を思い浮かべてもイイ。対して、キャンプとはやさしいシニシズムであり、快楽を欲しているから消化にいいのだ、ということになる。
『M*A*S*H』DVD特別編を観る。何度観ても、ドナルド・サザーランドの迷彩帽はダンディだし、例のエリオット・グールドがマティーニにオリーブを放り込むシーンには思わず膝を打ってしまう。サザーランドはカナダ出身、イギリスで舞台俳優としてデビュー、グールドはニューヨーク出身のユダヤ人でやはり舞台俳優。二人ともこの映画がきっかけで人気俳優となった。原作は朝鮮戦争を舞台にしたカートゥーンで、それに大胆&強烈なおふざけ感を加味したもの。1970年に公開され大ヒット、カンヌ映画祭でグランプリも取っている。当時はヴェトナム戦争まっただ中。一応朝鮮戦争を描いているのだが、見るうちにどうしてもヴェトナム戦争を連想してしまうところが監督ロバート・アルトマンの狙いだったようだ。それにしても、前述の2人が、軍隊という「真面目であるべき場」で演じる不真面目さがサイコーだ。それは、スーザン・ソンタグがいっている「キャンプな感覚」に近い。ソンタグは著書『反解釈』の中で「われわれは、不真面目なものについて真面目になることもできれば、真面目なものについて不真面目になることもできるのである」、といっている。ソンタグは又、対照的にポップ・アートについてこういっている、「キャンプと関係があるとしても、やはり平板で乾いており、真面目であり、究極においてニヒリスティックである」。これは、もちろんアンディ・ウォーホルを思い浮かべてもイイし”King Of Pop”と呼ばれることになった人を思い浮かべてもイイ。対して、キャンプとはやさしいシニシズムであり、快楽を欲しているから消化にいいのだ、ということになる。
 「タフでいることにはもうヘトヘトなの・・・」。訥々(とつとつ)とした生ギターをバックに、舌っ足らずのチャーミングな声が耳元でささやく。歌っているのはニューヨーク出身の女性シンガー&ソングライター、メレデス・ゴドルー。まるでアメリカのインディペンデント映画の主人公のように、リアルだ。
「タフでいることにはもうヘトヘトなの・・・」。訥々(とつとつ)とした生ギターをバックに、舌っ足らずのチャーミングな声が耳元でささやく。歌っているのはニューヨーク出身の女性シンガー&ソングライター、メレデス・ゴドルー。まるでアメリカのインディペンデント映画の主人公のように、リアルだ。