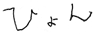再発ブーム
April 9th, 2011
 久しぶりのコペンハーゲンは、あいにく冷たい雨だった。でも大丈夫、いつもお世話になっているお宅に到着すると、家具デザイナーであるTさんと奥様が笑顔で出迎えてくれる。長旅の疲れがスーと消える瞬間だ。荷ほどきをする間もなくウエルカム・ワインで乾杯。近況を語り合うのももどかしく「最近の再発ブーム」についてTさんが話の口火を切る。まだボンヤリしている頭にハッパを掛けながら聞いてみると、思い当たることも多い。様々な名作といわれる椅子や照明、デザイン・アイコンな作品の再発がこの数年堰を切ったように続いている。もちろん、きちんとしたものもあるが、残念なことに形だけを、それも乱暴になぞっただけのようなものも少なくない。一般的に著作権は50年とされているが、量産可能な家具などが著作物と認められるケースは非常に少なく、たとえ意匠権を取得していてもなかなか機能しないのが現状らしい。でも、Tさんが言いたいことはどうやらそんなことではないようだ。それは、北欧家具を生み出したデンマークが、旧作の復刻に熱心なあまり、本家としての求心力を失うのではないかという危機感のように聞こえる。たしかに、新製品の開発には多大なコストとリスクがともなう。ついつい過去のヒット作を、今的なカラーやサイズに見直してリメイクするほうが手っ取り早いにちがいない。でもそれは、デザイナーと職人が協力してつちかってきたデンマーク・クラフトの力を削ぐことになりはしないか、という危惧なのだろう。目指すべきことは、安易な反復ではなく、本来持っていた価値への気づきであり、回復への思いを込めた工夫ということなのか。40年前、ひとりでこの地へやって来て以来、デザイナーであり、なにより職人という矜持を持ちながら仕事をする人らしい話だ。そういえば、Tさんがデザインした木馬には、あのカイ・ボイセンの名作へのオマージュを越えた、彼の真骨頂が感じられるのである。
久しぶりのコペンハーゲンは、あいにく冷たい雨だった。でも大丈夫、いつもお世話になっているお宅に到着すると、家具デザイナーであるTさんと奥様が笑顔で出迎えてくれる。長旅の疲れがスーと消える瞬間だ。荷ほどきをする間もなくウエルカム・ワインで乾杯。近況を語り合うのももどかしく「最近の再発ブーム」についてTさんが話の口火を切る。まだボンヤリしている頭にハッパを掛けながら聞いてみると、思い当たることも多い。様々な名作といわれる椅子や照明、デザイン・アイコンな作品の再発がこの数年堰を切ったように続いている。もちろん、きちんとしたものもあるが、残念なことに形だけを、それも乱暴になぞっただけのようなものも少なくない。一般的に著作権は50年とされているが、量産可能な家具などが著作物と認められるケースは非常に少なく、たとえ意匠権を取得していてもなかなか機能しないのが現状らしい。でも、Tさんが言いたいことはどうやらそんなことではないようだ。それは、北欧家具を生み出したデンマークが、旧作の復刻に熱心なあまり、本家としての求心力を失うのではないかという危機感のように聞こえる。たしかに、新製品の開発には多大なコストとリスクがともなう。ついつい過去のヒット作を、今的なカラーやサイズに見直してリメイクするほうが手っ取り早いにちがいない。でもそれは、デザイナーと職人が協力してつちかってきたデンマーク・クラフトの力を削ぐことになりはしないか、という危惧なのだろう。目指すべきことは、安易な反復ではなく、本来持っていた価値への気づきであり、回復への思いを込めた工夫ということなのか。40年前、ひとりでこの地へやって来て以来、デザイナーであり、なにより職人という矜持を持ちながら仕事をする人らしい話だ。そういえば、Tさんがデザインした木馬には、あのカイ・ボイセンの名作へのオマージュを越えた、彼の真骨頂が感じられるのである。
ローズ・キャバット。
February 18th, 2011
 ツーソンにあるローズ・キャバットのスタジオは、アリゾナ大学に近い静かな住宅街のなかにポツンとたたずんでいる。おかげで、遠くから訪ねてきた気負いみたいなものがスッカリ消えてしまった。そのうえ、事前の連絡通り、彼女は自宅からこのスタジオまで出向いてくれていて、僕らを笑顔で出迎えてくれたのだ。
ツーソンにあるローズ・キャバットのスタジオは、アリゾナ大学に近い静かな住宅街のなかにポツンとたたずんでいる。おかげで、遠くから訪ねてきた気負いみたいなものがスッカリ消えてしまった。そのうえ、事前の連絡通り、彼女は自宅からこのスタジオまで出向いてくれていて、僕らを笑顔で出迎えてくれたのだ。
96才である。さすがに足腰が少し不自由な為に車いすを使ってはいるものの、「手先の衰えはなく、作品も作ってるのよ」と娘さんが笑う。確かに、長いあいだ手を使ってきた人らしく頭はシャープ。それから小一時間あまりの間、様々なトピックをジョーク混じりにおしゃべりしてくれた。そのほとんどは画家で商業デザイナーだった亡き夫との思い出なのだが、ふたりは幼なじみで生涯にわたって良きコラボレーターであり、かけがえのないライバルだったようである。
ある日、たまたま陶土を手ひねりでポットに仕立て上げたのを見た夫が驚き、彼の薦めもあって職業訓練校に通い始め、そこで初めて蹴ロクロに触れたらしい。
「最初の頃は夫が絵付けをしていたの。でも、それじゃ私の作品じゃないと思って、自分なりにやることにしたの」
その後、様々なフォルムや釉薬の実験をかさね、いわば「トライアル&エラー」の結果として1960年代に誕生したのが、代表作である一連の”Feelies”と彼女が呼んでいる作品である。果物や野菜など、オーガニックな気配を感じさせる独特のフォルムと釉薬は、とてもエモーショナルで自由さに満ちている。そして、実際に手に触れることで、その独特のすべすべした「フィーリング」に驚くことになる。
ぼくは、思わず聞かずにはいられなかった。
「キャバットさんは北欧の陶器に興味はおありですか?」
「カトラリーとかデザインは好きだけれど、陶器はどうしても冷たい感じがしてしまうの」との答えだった。なるほど。
正直にいうと、ぼくはそれほどキャバットに熱心ではなかったかもしれない。しかし、信頼しているdieciの田丸さんから話を聞くにつれ、とにかく実物を見てみたくなり、やって来たのである。そしてキャバットの世界をとても楽しんでしまった。ツーソンの、まるで西部劇の舞台のような青い空の下で作陶をする彼女は、その名の通り、砂漠に咲いた一輪のバラだった。
”GRAVEL & GOLD”
February 17th, 2011
 結果として、もっとも望ましいのは写真のように前置きなしのシンプルな店名。前述したグラハム・ナッシュの娘さんが友人3人で運営している店なのだけれど、直訳すれば「砂利と黄金」ってところだろうか。多分、「ジャンクかお宝か、自分の目で確かめてください」ということなのだろう。ゴールドラッシュでにぎわったサンフランシスコらしいネーミングでもある。売っているモノは様々な生活雑貨や本、古着や新品の衣料で、その中にはセント・ジェイムスやカンケン・バッグなどヨーロッパものも。すごく斬新ってわけではないけれど、とても好ましい雰囲気が流れている。忘れられないのは、スタッフの自然な笑顔と何気ない声かけ。気になったバッファロー・プレインのジャケットを試着した際、ローカルなフリーマーケットの情報を教えていただきました。ウチも見習わなければ。
結果として、もっとも望ましいのは写真のように前置きなしのシンプルな店名。前述したグラハム・ナッシュの娘さんが友人3人で運営している店なのだけれど、直訳すれば「砂利と黄金」ってところだろうか。多分、「ジャンクかお宝か、自分の目で確かめてください」ということなのだろう。ゴールドラッシュでにぎわったサンフランシスコらしいネーミングでもある。売っているモノは様々な生活雑貨や本、古着や新品の衣料で、その中にはセント・ジェイムスやカンケン・バッグなどヨーロッパものも。すごく斬新ってわけではないけれど、とても好ましい雰囲気が流れている。忘れられないのは、スタッフの自然な笑顔と何気ない声かけ。気になったバッファロー・プレインのジャケットを試着した際、ローカルなフリーマーケットの情報を教えていただきました。ウチも見習わなければ。
キュリオシティ・ショップ
February 16th, 2011
 もひとつ、ショップのカテゴライズで気になったのが”Curiosity Shop”というもの。だいたい僕らの商売を何と自称するかについては、案外頭を悩ませるわけです。「アンティック・ショップ」というほど古いものを扱っているわけではないし、「セレクト・ショップ」じゃ物足りないしね。サンフランシスコのミッション地区を歩いていてこの言葉に出会ったときは、「これイタダキ」と思った次第。そういえば、北欧にもこの言葉を冠している店が案外多い。「あなたの好奇心をくすぐる店」ってな感じなんだろうか。古いものやモダンなものを取り混ぜ、そこに店主の独断を混入する手口です。でも、好奇心も千差万別、店に入った途端「こりゃダメだ」ってのもあります。この店は、古い(といっても50年代くらいか)バスケのボールを何気に転がしてて確かにくすぐられたんですが…。
もひとつ、ショップのカテゴライズで気になったのが”Curiosity Shop”というもの。だいたい僕らの商売を何と自称するかについては、案外頭を悩ませるわけです。「アンティック・ショップ」というほど古いものを扱っているわけではないし、「セレクト・ショップ」じゃ物足りないしね。サンフランシスコのミッション地区を歩いていてこの言葉に出会ったときは、「これイタダキ」と思った次第。そういえば、北欧にもこの言葉を冠している店が案外多い。「あなたの好奇心をくすぐる店」ってな感じなんだろうか。古いものやモダンなものを取り混ぜ、そこに店主の独断を混入する手口です。でも、好奇心も千差万別、店に入った途端「こりゃダメだ」ってのもあります。この店は、古い(といっても50年代くらいか)バスケのボールを何気に転がしてて確かにくすぐられたんですが…。
ゼネラルストア。
February 16th, 2011
 去年マウイ島のへんぴな場所にある「ハセガワ・ジェネラルストア」に行った頃から気なっていたのだけれど、今回アメリカ西海岸でも「ジェネラルストア」に出会った。まずLAにある大好きな店「トータス」が日常使いな日本製品を展開する新しい店の名前が「トータス・ジェネラルストア」だったし、サンフランシスコの、これもへんぴな場所にある今注目の雑貨屋はズバリ「ジェネラルストア」だった。日本語ではたぶん「よろず屋」ってところか。暮らしに寄り添う、色んなモノが手に入る便利な店で、今的には「コンビニ」みたいなものだろうか。ただし、どこにでもあって、同じような商品構成でマニュアル化されたコンビニと真逆であることはいうまでもない。個人的な主観に基づいた、刺激的な品揃えが勝負どころなのである。したがって、「ジェネラル(一般的)」とはいっても、かならずしも万人受けを狙ったものではない。これも一種の「カウンター・カルチャー」的発想なのだろうか、アメリカ人はネーミングがウマイな。そういえば、日本にも「ジェネラル」という家電メーカーがあったよね。うちの母は「ゼネラル」って呼んでたけれど。
去年マウイ島のへんぴな場所にある「ハセガワ・ジェネラルストア」に行った頃から気なっていたのだけれど、今回アメリカ西海岸でも「ジェネラルストア」に出会った。まずLAにある大好きな店「トータス」が日常使いな日本製品を展開する新しい店の名前が「トータス・ジェネラルストア」だったし、サンフランシスコの、これもへんぴな場所にある今注目の雑貨屋はズバリ「ジェネラルストア」だった。日本語ではたぶん「よろず屋」ってところか。暮らしに寄り添う、色んなモノが手に入る便利な店で、今的には「コンビニ」みたいなものだろうか。ただし、どこにでもあって、同じような商品構成でマニュアル化されたコンビニと真逆であることはいうまでもない。個人的な主観に基づいた、刺激的な品揃えが勝負どころなのである。したがって、「ジェネラル(一般的)」とはいっても、かならずしも万人受けを狙ったものではない。これも一種の「カウンター・カルチャー」的発想なのだろうか、アメリカ人はネーミングがウマイな。そういえば、日本にも「ジェネラル」という家電メーカーがあったよね。うちの母は「ゼネラル」って呼んでたけれど。
ローカル・ビールが旨い。
February 15th, 2011
 西海岸へ行くのでお薦めのワインを教えて欲しい、と轟きさんに尋ねたところ、「ビールが面白いですよ」とのことだった。アメリカのビールと言えばバドワイザーしか思い浮かばないので意外だった。どうやら小規模の作り手によるローカル・ビールのことらしい。ビールはあまり飲まない口でもあり、あまり気のない返事をしたように思う。ところが、サンフランシスコのアウターランドというカフェで飲んでみて、その美味しさにビックリ。同行した鄕古さんのビール好きのおかげ。彼がオーダーしたのは褐色で11度くらいだったか、ひとくち飲ませてもらったらすこぶる個性的で旨い。これならガブガブ飲まなくとも酔える。早速ぼくと野見山君がおのおの頼んで効きビールとなった次第。コップもジャムのジャーかなんかを使ってるところが気分いい。場所はジェネラル・ストアのすぐそば。もちろんランチも美味しかったです。
西海岸へ行くのでお薦めのワインを教えて欲しい、と轟きさんに尋ねたところ、「ビールが面白いですよ」とのことだった。アメリカのビールと言えばバドワイザーしか思い浮かばないので意外だった。どうやら小規模の作り手によるローカル・ビールのことらしい。ビールはあまり飲まない口でもあり、あまり気のない返事をしたように思う。ところが、サンフランシスコのアウターランドというカフェで飲んでみて、その美味しさにビックリ。同行した鄕古さんのビール好きのおかげ。彼がオーダーしたのは褐色で11度くらいだったか、ひとくち飲ませてもらったらすこぶる個性的で旨い。これならガブガブ飲まなくとも酔える。早速ぼくと野見山君がおのおの頼んで効きビールとなった次第。コップもジャムのジャーかなんかを使ってるところが気分いい。場所はジェネラル・ストアのすぐそば。もちろんランチも美味しかったです。
アリゾナの歓迎ぶり。
February 14th, 2011
 ロスアンジェルスからアリゾナのツーソンへは車で約8時間くらいか。当初はインターステイツ10でパームスプリングス経由を考えていたのだけれど、インターチェンジを間違えて8に乗ってしまい、結局南経由で向かうことになった。といってもロングドライブであることに変わりはない。どうせ今日は移動日と決めていたわけだし、真っ青の空の下、広大な大地をひた走るのもアメリカならではの醍醐味だろう。サンディエゴあたりから東へ折れると次第に風景が変化し始める。少しづつ坂を登っているのだろうか、荒涼とした風景の中にむき出しの岩が迫ってくる。”Sidewinder Road”なんて標識が目にはいった。まさか「ガラガラヘビの獣道」などあるわけはないが、もしこんなところをひとりで歩けといわれてもお断りすることは間違いない。「ふたりの男がこんな荒野をひたすら歩いて、道に迷って一人が死んじゃう映画、なんだっけ?」と奥さんに尋ねると、「『ジェリー』じゃない?たしかガス・ヴァン・サントだったと思う」との返事。ああ、そうだった。まったく、人間の方向感覚ほどあてにならないものはない。車内にはおとといayaさんからいただいたグラハム・ナッシュのトリビュートCDが流れている。アルバムタイトルの”Be Yourself”がかかると、突然、高円寺の6畳一間の部屋でヘッドフォンを耳に押し当てながら聴いていた頃がフラッシュバックした。この曲が入っていた”Songs For Beginners”というLPは親友からの借り物だったけど、とても気に入ってしまって返すのをズルズルと先延ばししたっけ。なにしろ、”Chicago”や”Military Madness ”なんていう強いメッセージを持つ曲も、彼の手に掛かると、つい口ずさみたくなってしまうから不思議だ。ぼくは、CSN&Yというユニットではニール・ヤングとグラハム・ナッシュにシンパシーを感じていた。そうそう、ayaさんに初めて紹介され、次号YODELのインタビューをしていた時のことだった。彼女が小屋を借りているというトパンガ・キャニオンには昔ニール・ヤングが住んでいたことが話しのきっかけになった。それからグラハム・ナッシュの娘が父のトリビュート・アルバムを作ったこと、そしてその2,3日前に訪れたサンフランシスコのミッション地区にある”Gravel And Gold”というとてもイイ感じの店は、実は彼女が経営していることを聞いたのだった。グラハム・ナッシュのことは、ずっと忘れていたのだけれど、そのアルバムを聴いてみたいという顔をしたのだろう、彼女は翌日会ったときに焼き付けのCDをプレゼントしてくれた。そんなことをボンヤリ思っていると、後ろからサイレンの音、ハイウェイ・パトロールではないか! それから20分ほど、赤ら顔に口ひげを蓄えた警官は僕らにタップリ説教をしたあと、ニコリともせずにスピード違反のキップを切ってくれた。75マイル制限を13マイルオーヴァーで、たしか168ドルの罰金。さすがにアリゾナ、歓迎ぶりが手厳しい。
ロスアンジェルスからアリゾナのツーソンへは車で約8時間くらいか。当初はインターステイツ10でパームスプリングス経由を考えていたのだけれど、インターチェンジを間違えて8に乗ってしまい、結局南経由で向かうことになった。といってもロングドライブであることに変わりはない。どうせ今日は移動日と決めていたわけだし、真っ青の空の下、広大な大地をひた走るのもアメリカならではの醍醐味だろう。サンディエゴあたりから東へ折れると次第に風景が変化し始める。少しづつ坂を登っているのだろうか、荒涼とした風景の中にむき出しの岩が迫ってくる。”Sidewinder Road”なんて標識が目にはいった。まさか「ガラガラヘビの獣道」などあるわけはないが、もしこんなところをひとりで歩けといわれてもお断りすることは間違いない。「ふたりの男がこんな荒野をひたすら歩いて、道に迷って一人が死んじゃう映画、なんだっけ?」と奥さんに尋ねると、「『ジェリー』じゃない?たしかガス・ヴァン・サントだったと思う」との返事。ああ、そうだった。まったく、人間の方向感覚ほどあてにならないものはない。車内にはおとといayaさんからいただいたグラハム・ナッシュのトリビュートCDが流れている。アルバムタイトルの”Be Yourself”がかかると、突然、高円寺の6畳一間の部屋でヘッドフォンを耳に押し当てながら聴いていた頃がフラッシュバックした。この曲が入っていた”Songs For Beginners”というLPは親友からの借り物だったけど、とても気に入ってしまって返すのをズルズルと先延ばししたっけ。なにしろ、”Chicago”や”Military Madness ”なんていう強いメッセージを持つ曲も、彼の手に掛かると、つい口ずさみたくなってしまうから不思議だ。ぼくは、CSN&Yというユニットではニール・ヤングとグラハム・ナッシュにシンパシーを感じていた。そうそう、ayaさんに初めて紹介され、次号YODELのインタビューをしていた時のことだった。彼女が小屋を借りているというトパンガ・キャニオンには昔ニール・ヤングが住んでいたことが話しのきっかけになった。それからグラハム・ナッシュの娘が父のトリビュート・アルバムを作ったこと、そしてその2,3日前に訪れたサンフランシスコのミッション地区にある”Gravel And Gold”というとてもイイ感じの店は、実は彼女が経営していることを聞いたのだった。グラハム・ナッシュのことは、ずっと忘れていたのだけれど、そのアルバムを聴いてみたいという顔をしたのだろう、彼女は翌日会ったときに焼き付けのCDをプレゼントしてくれた。そんなことをボンヤリ思っていると、後ろからサイレンの音、ハイウェイ・パトロールではないか! それから20分ほど、赤ら顔に口ひげを蓄えた警官は僕らにタップリ説教をしたあと、ニコリともせずにスピード違反のキップを切ってくれた。75マイル制限を13マイルオーヴァーで、たしか168ドルの罰金。さすがにアリゾナ、歓迎ぶりが手厳しい。
距離感
January 31st, 2011
 初めてアメリカへ行ったのは、高校生のころ。自宅から私鉄に乗り3つ目の駅で下車し、そこから徒歩でたったの15分だった。そこは通称「春日原ベースキャンプ」と呼ばれた米軍の敷地で、僕らの間では、住所登録は実のところカリフォルニアだと信じられていた。僕らというのは、当時一緒にバンドを組んでいた4人の仲間で、『ルート66』というあまりハッピーじゃないアメリカTVドラマに夢中で、学校では明らかに浮いた存在だった。そのうちの一人がどこから聞きつけてきたのか独立記念日には基地が一般に開放されるというニュースを耳打ちした。その日はバザーが開かれたり、バンドの演奏が聞けたりするという。もちろん異議なしというわけで、お気に入りの女の子がいるヤツはその娘に声を掛けつつ、ワクワクしながらその日を待っていた。
初めてアメリカへ行ったのは、高校生のころ。自宅から私鉄に乗り3つ目の駅で下車し、そこから徒歩でたったの15分だった。そこは通称「春日原ベースキャンプ」と呼ばれた米軍の敷地で、僕らの間では、住所登録は実のところカリフォルニアだと信じられていた。僕らというのは、当時一緒にバンドを組んでいた4人の仲間で、『ルート66』というあまりハッピーじゃないアメリカTVドラマに夢中で、学校では明らかに浮いた存在だった。そのうちの一人がどこから聞きつけてきたのか独立記念日には基地が一般に開放されるというニュースを耳打ちした。その日はバザーが開かれたり、バンドの演奏が聞けたりするという。もちろん異議なしというわけで、お気に入りの女の子がいるヤツはその娘に声を掛けつつ、ワクワクしながらその日を待っていた。
その少し前、九電記念体育館で行われたビーチ・ボーイズのコンサートの帰り道でのことだ。初めての外タレ経験にすっかり興奮気味だった僕は、帰りの電車の中で彼らのヒット曲を小さく口ずさんでいた。すると、隣に立っていた若い外人さんが「ランランギルラン、アギルラン〜」とハモってくれるではないか! 多分、同じコンサート帰りなのだろうが、なにしろ突然の御唱和である。僕は完全にアセってしまい、ニッコリ笑って向こうを向いてしまった。彼は私服だったけど髪型はいわゆるGIカットだし、当時の福岡では米軍関係以外の外人を見かけることはなく、しかも電車は春日原方面へ向かっていたわけで、彼がキャンプからやってきたことを勝手に確信したのだった。つまり、そのランラン君に会えるかも、という淡い希望もあったのだろうか。
基地のゲートを抜け、敷地内にはいると、そこはアッケラカンとアメリカだった。広い芝生の間に点在するハウスを見て、その中に『うちのママは世界一』 や『パパ大好き』みたいな暮らしを想像した。庭にはバスケット・ボールのシュート板があったり、バーベキューセットが転がっていたりと、たしかに資本主義の豊かな暮らしを連想させてくれた。僕らは、まるで初めてのディズニーランドのようにキョロキョロしながら、いつしか重厚な造りの将校倶楽部に迷い込んでいた。そこで、生まれて初めて飲んだジンジャエールに、甘ったるいコカコーラとは違うヒリヒリとした辛い味を知ったのだった。
ここには、戦争中には飛行機を作る軍需工場があって、僕の母も動員されて働いていたと聞いた覚えがある。そして、戦後はアメリカ軍の基地となり、 僕が生まれた翌年の1950年には朝鮮戦争が勃発し、近くの板付飛行場は後方支援として重要な役割を果たしていたらしい。そして、僕らが闖入した1960年代半ばといえば、アメリカがベトナムに本格的に介入していた頃だったはずだ。それから30年以上が経過した夏、いまでは広大な総合運動公園になったその場所を横切ってハローワークへ行った。勤めていた仕事を辞め、失業保険を受け取るためだった。
あさってからアメリカ西海岸へ行くことになっている。現実のアメリカへは飛行時間10時間あまり。遠いような、そうでもないような、不思議な距離感である。
過ぎたるはナントカ。
January 25th, 2011
 デニムのシャンブレー・シャツを買った。orSlowというメーカーのもので、とても良くできている。生地感、縫製などアメリカのワークシャツの基本を押さえた作りで、デッドストックかと見間違うほど。去年の夏、アメリカ海軍モデルのタンガリー・ファティーグ・パンツを買って気に入ったからなのだが、考えてみると、出会いは少しさかのぼる。たしか3年ほど前か、STOCKISTSにENOUGHとして参加した際に彼らのブースを覗いた。そのときは、なんで古着を出してるんだろう、と不思議に思って尋ねると、オリジナルだとのことで「へぇー」と、ミョーに感心というかあきれた覚えがある。レプリカにはあまり興味が持てないほうなので、熱意みたいなものは伝わったけれど、あえて試着までは試みなかったのだ。ところが、着てみて分かったのだけれど、リ・サイズがとても上手なのである。古着というものは、いくら気に入っても大体サイズが大きすぎて断念することが多い。貧弱な我が肉体でもなんとかなって、その上、充分こだわりもあるわけで、なんだか嬉しくなるわけだ。このシャツもこれから春、夏を迎えて大活躍しそうで楽しみである。ただひとつ、こだわりが過ぎていると思われる部分がある。両脇の裾部分にマチが取ってあるのは良しとして、なにやら糸が3本づつ垂れ下がっているのだ。ラフさや経年を演出したものかと思われるのだが、さてこのまま着ようか、切ってしまおうか、おおいに迷っている。せっかくだから、当分はまんまのような気もするが。
デニムのシャンブレー・シャツを買った。orSlowというメーカーのもので、とても良くできている。生地感、縫製などアメリカのワークシャツの基本を押さえた作りで、デッドストックかと見間違うほど。去年の夏、アメリカ海軍モデルのタンガリー・ファティーグ・パンツを買って気に入ったからなのだが、考えてみると、出会いは少しさかのぼる。たしか3年ほど前か、STOCKISTSにENOUGHとして参加した際に彼らのブースを覗いた。そのときは、なんで古着を出してるんだろう、と不思議に思って尋ねると、オリジナルだとのことで「へぇー」と、ミョーに感心というかあきれた覚えがある。レプリカにはあまり興味が持てないほうなので、熱意みたいなものは伝わったけれど、あえて試着までは試みなかったのだ。ところが、着てみて分かったのだけれど、リ・サイズがとても上手なのである。古着というものは、いくら気に入っても大体サイズが大きすぎて断念することが多い。貧弱な我が肉体でもなんとかなって、その上、充分こだわりもあるわけで、なんだか嬉しくなるわけだ。このシャツもこれから春、夏を迎えて大活躍しそうで楽しみである。ただひとつ、こだわりが過ぎていると思われる部分がある。両脇の裾部分にマチが取ってあるのは良しとして、なにやら糸が3本づつ垂れ下がっているのだ。ラフさや経年を演出したものかと思われるのだが、さてこのまま着ようか、切ってしまおうか、おおいに迷っている。せっかくだから、当分はまんまのような気もするが。
物故
January 22nd, 2011
 いま読んでいる『装飾とデザイン(山崎正和)』という本によると、「もの」には、実のところ形がないらしい。たとえば、僕らが思い浮かべる「鉄というもの」は、鉄鋼だったりするのだけれど、それはものではなく、材料ということになる。設計に基付いてデザインされ、使用を目的とした意図がそなわっているというわけだ。つまり「それ以前の形のない鉄は知的な抽象の産物であり、形あるさまざまな鉄に共通する性質としてしか認識できない(引用)」ということらしい。一方、『星のあひびき(丸谷才一)』によると、「もののあはれ」と言うときの「もの」とは「さだめ、きまり」だとしている。『万葉集』の「紅(くれない)は移ろうものそ」は「紅は褪せるきまり」なのである(引用)、ということなのか。
いま読んでいる『装飾とデザイン(山崎正和)』という本によると、「もの」には、実のところ形がないらしい。たとえば、僕らが思い浮かべる「鉄というもの」は、鉄鋼だったりするのだけれど、それはものではなく、材料ということになる。設計に基付いてデザインされ、使用を目的とした意図がそなわっているというわけだ。つまり「それ以前の形のない鉄は知的な抽象の産物であり、形あるさまざまな鉄に共通する性質としてしか認識できない(引用)」ということらしい。一方、『星のあひびき(丸谷才一)』によると、「もののあはれ」と言うときの「もの」とは「さだめ、きまり」だとしている。『万葉集』の「紅(くれない)は移ろうものそ」は「紅は褪せるきまり」なのである(引用)、ということなのか。
さて、親しかった友人が先日突然他界した。中学時代に知り合い、音楽、映画、ファッション、異性など、青臭い時代に必須な事々をほとんど共有した。といっても、性格はほぼ正反対。せっかちで小心な僕とは違い、約束事が苦手でのんびり屋で辛辣なユーモアが得意だった彼は、不良達からも一目置かれる存在だった。タバコを吸い始めたのも、女性をモノにしたのも彼の方が早かった。出会いから大学の卒業まで、僕らはちょっとした”Odd Couple”だったと思っている(どちらがジャック・レモンとウォールター・マッソーだったかは言わずもがな)。
やがて僕がバンドを組んだ頃、彼は故郷に戻ってロック喫茶を始めた。ひょっとすると、東京でムーヴィンやブラックホークに通っていた時代の気分を福岡に持ち込んでみたかったのかもしれない。でも、商売に向いてるとはいえない性格もあって、生涯3軒やった店はどれも経営的には難しかった。もちろん、若い音楽好きな人達を、独特な磁力で惹き付けるという役割は果たしてくれたのだが。
人が死ぬ為に用意された言葉は意外に多い。死亡、死去、永眠、他界など比較的聞き慣れたものから、逝去、永逝、長逝などという詩的なものもあり、絶息、絶命、お陀仏なんてリアルなものもある。それだけ人の死は、その人の生に付随した「よしなし事」が多いということなのだろう。そこで、いったい彼にふさわしい通知は何だろう、と考えてみた。「物故」しかない、と思った。「さだめが過ぎる」というわけだ。
あたかも「事故」に近しいこの言葉面通り、彼は孤独に終えた。でも、こんなことを言ってはなんだが、とても彼らしい選択だったのではないか。些末な事情はさておいて、彼を知る人にとって、そのことはかならずしも義憤にかられるような不条理な出来事ではなかった、と思う。でも、やりきれなさは残ってしまう。彼の自前のニックネームはRoji。由来がトム・ウエイツの曲名だったか、はつみつぱいの『煙草路地』だったのか、もう尋ねるすべはない。
 久しぶりのコペンハーゲンは、あいにく冷たい雨だった。でも大丈夫、いつもお世話になっているお宅に到着すると、家具デザイナーであるTさんと奥様が笑顔で出迎えてくれる。長旅の疲れがスーと消える瞬間だ。荷ほどきをする間もなくウエルカム・ワインで乾杯。近況を語り合うのももどかしく「最近の再発ブーム」についてTさんが話の口火を切る。まだボンヤリしている頭にハッパを掛けながら聞いてみると、思い当たることも多い。様々な名作といわれる椅子や照明、デザイン・アイコンな作品の再発がこの数年堰を切ったように続いている。もちろん、きちんとしたものもあるが、残念なことに形だけを、それも乱暴になぞっただけのようなものも少なくない。一般的に著作権は50年とされているが、量産可能な家具などが著作物と認められるケースは非常に少なく、たとえ意匠権を取得していてもなかなか機能しないのが現状らしい。でも、Tさんが言いたいことはどうやらそんなことではないようだ。それは、北欧家具を生み出したデンマークが、旧作の復刻に熱心なあまり、本家としての求心力を失うのではないかという危機感のように聞こえる。たしかに、新製品の開発には多大なコストとリスクがともなう。ついつい過去のヒット作を、今的なカラーやサイズに見直してリメイクするほうが手っ取り早いにちがいない。でもそれは、デザイナーと職人が協力してつちかってきたデンマーク・クラフトの力を削ぐことになりはしないか、という危惧なのだろう。目指すべきことは、安易な反復ではなく、本来持っていた価値への気づきであり、回復への思いを込めた工夫ということなのか。40年前、ひとりでこの地へやって来て以来、デザイナーであり、なにより職人という矜持を持ちながら仕事をする人らしい話だ。そういえば、Tさんがデザインした木馬には、あのカイ・ボイセンの名作へのオマージュを越えた、彼の真骨頂が感じられるのである。
久しぶりのコペンハーゲンは、あいにく冷たい雨だった。でも大丈夫、いつもお世話になっているお宅に到着すると、家具デザイナーであるTさんと奥様が笑顔で出迎えてくれる。長旅の疲れがスーと消える瞬間だ。荷ほどきをする間もなくウエルカム・ワインで乾杯。近況を語り合うのももどかしく「最近の再発ブーム」についてTさんが話の口火を切る。まだボンヤリしている頭にハッパを掛けながら聞いてみると、思い当たることも多い。様々な名作といわれる椅子や照明、デザイン・アイコンな作品の再発がこの数年堰を切ったように続いている。もちろん、きちんとしたものもあるが、残念なことに形だけを、それも乱暴になぞっただけのようなものも少なくない。一般的に著作権は50年とされているが、量産可能な家具などが著作物と認められるケースは非常に少なく、たとえ意匠権を取得していてもなかなか機能しないのが現状らしい。でも、Tさんが言いたいことはどうやらそんなことではないようだ。それは、北欧家具を生み出したデンマークが、旧作の復刻に熱心なあまり、本家としての求心力を失うのではないかという危機感のように聞こえる。たしかに、新製品の開発には多大なコストとリスクがともなう。ついつい過去のヒット作を、今的なカラーやサイズに見直してリメイクするほうが手っ取り早いにちがいない。でもそれは、デザイナーと職人が協力してつちかってきたデンマーク・クラフトの力を削ぐことになりはしないか、という危惧なのだろう。目指すべきことは、安易な反復ではなく、本来持っていた価値への気づきであり、回復への思いを込めた工夫ということなのか。40年前、ひとりでこの地へやって来て以来、デザイナーであり、なにより職人という矜持を持ちながら仕事をする人らしい話だ。そういえば、Tさんがデザインした木馬には、あのカイ・ボイセンの名作へのオマージュを越えた、彼の真骨頂が感じられるのである。