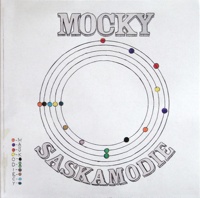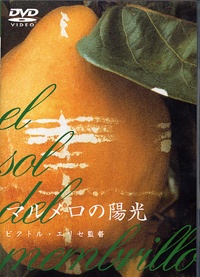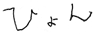「音のある休日」#2
July 31st, 2009
 ジョルジオ・トマ /マイ・ヴォーカリーズ・ファン・フェア
ジョルジオ・トマ /マイ・ヴォーカリーズ・ファン・フェア
「イタリアといえばカンツォーネ」とはいにしえの話。ジョルジオ・トゥマは南イタリアに住みながら、英語で端正なソフト・ロックを生み出した。今、世界中のポップスは確実にボーダーレス化している。
アントニオ・カルロス・ジョビンとブライアン・ウィルソンが好きだという彼らしく、アルバムはボサノバやうっとりするコーラスに彩られている。その上、60年代の艶笑イタリア映画のサントラのように甘酸っぱい哀愁が漂っているところがツボなのだ。やはり、出自は隠せないものと見た。しっかり練られたアレンジとさわやかな演奏に、耳の肥えたリスナーもハッピーな気分になってしまうこと請け合い。梅雨空も、まんざら悪くない気分だ。
(西日本新聞 6月28日朝刊)
「音のある休日」#1
July 31st, 2009
6月から西日本新聞の日曜版文化面で始まった「音のある休日」という小さなCD紹介コラムを、隔週で書かせていただいている。「週末にくつろいでもらうために、現在入手可能なCDを紹介する」という主旨で、ジャンルにこだわらなくていいという前提でお引き受けした。おかげで、またポップスをちゃんと聞いてみるきっかけになったと思う。よかったら読んでみてください。中にはorganで販売しているものもあります。
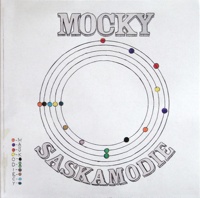
モッキー/サスカモォディ
ファイストやゴンザレス、ジェーン・バーキンなどの作品でも活躍するカナダ人ミュージシン、モッキー。60年代のソウルやジャズを思い起こさせるような新作は、ゆったりとしたメロウな演奏が主体だが、適度に混じる夢見がちなヴォイスやハミングも気持ちいい。トンガったクラブ系とは違い、どこかで聞いたことがあるような親密なメロディは、一人でぼんやり聞くのにもうってつけだ。
レコーディングはセルジュ・ゲンズブールも使っていたというパリのスタジオ。なるほど、時代を超えたかのようなヴィンテージ感が漂っているわけだ。長くつきあえそうな一枚である。
(6月14日、西日本新聞朝刊)
築26年
July 27th, 2009
 記録的な大雨のおかげで、店内の3個所から雨漏り発生。まあ、たいしたことはなかったのだが、このビルも築26年だからそろそろガタがきてもおかしくない。そうそう、西日本新聞によると「日本時間学会」という新しい学会が山口で産声を上げたらしい。「時間とは何か、時間はいつ生まれたのか」などというむずかしい理論ばかりではなく、生物時計のメカニズム、文学や芸術に現れた時間、アキレスと亀 『速さ』とは何か、退職者の時間感覚、などという面白そうなトピックもある。もちろん「老い」も。そういえば、昨日S君がやってきて、ダン・ヒックスの来日時のインタヴィユーが載ったフリーペーパーを持ってきてくれた。1941年アーカンソー生まれのサンフランシスコ育ち、現在67才。一時はアル中だったが、見事復帰を果たした現役の言葉が載っていた。「そうだねえ、フィジカルなことでは歯や耳の衰えとか、疲れとか色々あるけど、基本的にはエンジョイしてるよ。普通はリタイアして家に閉じこもっている年齢だとは思うけど、まだまだやることはあるし、いい人生を送っていると思う」。新聞には、ギリシャの政治家の言葉としてこうも書いてあった。「時間こそ最も賢明な相談相手である」と。築26年なんて、まだまだ現役続行と願いたい。
記録的な大雨のおかげで、店内の3個所から雨漏り発生。まあ、たいしたことはなかったのだが、このビルも築26年だからそろそろガタがきてもおかしくない。そうそう、西日本新聞によると「日本時間学会」という新しい学会が山口で産声を上げたらしい。「時間とは何か、時間はいつ生まれたのか」などというむずかしい理論ばかりではなく、生物時計のメカニズム、文学や芸術に現れた時間、アキレスと亀 『速さ』とは何か、退職者の時間感覚、などという面白そうなトピックもある。もちろん「老い」も。そういえば、昨日S君がやってきて、ダン・ヒックスの来日時のインタヴィユーが載ったフリーペーパーを持ってきてくれた。1941年アーカンソー生まれのサンフランシスコ育ち、現在67才。一時はアル中だったが、見事復帰を果たした現役の言葉が載っていた。「そうだねえ、フィジカルなことでは歯や耳の衰えとか、疲れとか色々あるけど、基本的にはエンジョイしてるよ。普通はリタイアして家に閉じこもっている年齢だとは思うけど、まだまだやることはあるし、いい人生を送っていると思う」。新聞には、ギリシャの政治家の言葉としてこうも書いてあった。「時間こそ最も賢明な相談相手である」と。築26年なんて、まだまだ現役続行と願いたい。
入道雲モクモク
July 14th, 2009
 昨日に続き、親戚お二人と一緒に福岡観光。入道雲モクモク夏空の下、こんな機会でもなければ登らない福岡タワーからの眺めは案外ナイスだ。東にはアイランドタワーが遠く小さく見える。でも奥さんの情報では、向こうの方が20mくらい高いらしい。今、33階では田中さんがモデルルーム内装の仕上げをしているはず。「おーい、大丈夫か!」と叫びたいが、聞こえるわけがない。「お疲れ様」と、心で感謝。お昼時になったので、「因幡うどん」渡辺通店へ。ここのうどんは昔から親しんだ典型的な博多うどんで、コシのない麺にやさしい汁なのでお年寄りにもピッタリ。丸天うどんといなり寿司をペロリ。最近はシコシコ讃岐うどんばかりで久しぶりだったのだが、やはり旨いと再確認。うどん好きのOさんが次回来福したら、ぜひ連れて行こう。さて、大トリは太宰府。といっても、今日から始まった「阿修羅展」ではない。まずは都府楼跡の隣にある「観世音寺」で天平時代へ思いを馳せ、一路天満宮の裏へと向かう。目指すは「お石茶屋」の梅ヶ枝餅である。そういえば、Oサン夫妻と一緒に来たのはいつ頃だったか?その時も、半ば強引に連れてきたような気がする。戸外の気持ちの良い風に吹かれて、焼きたての餅と冷たいお茶を飲んだらすっかり良い気持ちになってしまい、あやうく本殿へのお参りを忘れるところだった。気分はすっかり夏休みなのだ。
昨日に続き、親戚お二人と一緒に福岡観光。入道雲モクモク夏空の下、こんな機会でもなければ登らない福岡タワーからの眺めは案外ナイスだ。東にはアイランドタワーが遠く小さく見える。でも奥さんの情報では、向こうの方が20mくらい高いらしい。今、33階では田中さんがモデルルーム内装の仕上げをしているはず。「おーい、大丈夫か!」と叫びたいが、聞こえるわけがない。「お疲れ様」と、心で感謝。お昼時になったので、「因幡うどん」渡辺通店へ。ここのうどんは昔から親しんだ典型的な博多うどんで、コシのない麺にやさしい汁なのでお年寄りにもピッタリ。丸天うどんといなり寿司をペロリ。最近はシコシコ讃岐うどんばかりで久しぶりだったのだが、やはり旨いと再確認。うどん好きのOさんが次回来福したら、ぜひ連れて行こう。さて、大トリは太宰府。といっても、今日から始まった「阿修羅展」ではない。まずは都府楼跡の隣にある「観世音寺」で天平時代へ思いを馳せ、一路天満宮の裏へと向かう。目指すは「お石茶屋」の梅ヶ枝餅である。そういえば、Oサン夫妻と一緒に来たのはいつ頃だったか?その時も、半ば強引に連れてきたような気がする。戸外の気持ちの良い風に吹かれて、焼きたての餅と冷たいお茶を飲んだらすっかり良い気持ちになってしまい、あやうく本殿へのお参りを忘れるところだった。気分はすっかり夏休みなのだ。
咳
July 13th, 2009
 この季節になると、博多の町は締め込み姿のヒトがソーツクようになる。「山笠」だ。それぞれ自分が属する「流れ」の紋が入った絣を着た若衆達が、那珂川を越え、福岡のストリートを闊歩することがある。そんな光景は結構目立ってしまうのだが、同時に「ああ、夏が来たんだ」と納得もする。祭りにはあまり関心がないのだけれど、奥さんの親戚が来てくれたこともあり、久しぶりに川端商店街を一緒にソーツキ、櫛田神社まで足を伸ばすことになった。キッチュな飾り山をいくつか見物し、古くからある帽子屋さんに立ち寄り、多分デッドストックだろうタータンチェックのポークパイハットを試したりしながら、少しずつ目標の場所に近づいていった。「中州ぜんざい」である。頭の中は「宇治ぜんざい」を食べることばかりを考えていたのだ。白玉が入り、宇治茶がかかった本物のかき氷は、ここでしか味わえない。半ば強引に誘ったわけで、お二人は「いらない」と言われる。仕方がないので2つ注文し、僕が1つで残り1つを3人でシェアすることになった。小さな店だし、表では待っている人もいる。早くも食べ終わった3人に悪いと、あせって食べたせいで、氷を食べた後特有の咳が出てしまった。そういえば、昔の夏休み、近所の駄菓子屋のところてんも酢を入れすぎると、咳が出ていたっけ。
この季節になると、博多の町は締め込み姿のヒトがソーツクようになる。「山笠」だ。それぞれ自分が属する「流れ」の紋が入った絣を着た若衆達が、那珂川を越え、福岡のストリートを闊歩することがある。そんな光景は結構目立ってしまうのだが、同時に「ああ、夏が来たんだ」と納得もする。祭りにはあまり関心がないのだけれど、奥さんの親戚が来てくれたこともあり、久しぶりに川端商店街を一緒にソーツキ、櫛田神社まで足を伸ばすことになった。キッチュな飾り山をいくつか見物し、古くからある帽子屋さんに立ち寄り、多分デッドストックだろうタータンチェックのポークパイハットを試したりしながら、少しずつ目標の場所に近づいていった。「中州ぜんざい」である。頭の中は「宇治ぜんざい」を食べることばかりを考えていたのだ。白玉が入り、宇治茶がかかった本物のかき氷は、ここでしか味わえない。半ば強引に誘ったわけで、お二人は「いらない」と言われる。仕方がないので2つ注文し、僕が1つで残り1つを3人でシェアすることになった。小さな店だし、表では待っている人もいる。早くも食べ終わった3人に悪いと、あせって食べたせいで、氷を食べた後特有の咳が出てしまった。そういえば、昔の夏休み、近所の駄菓子屋のところてんも酢を入れすぎると、咳が出ていたっけ。
パーカー・ポージー
July 9th, 2009
 映画は冒頭が楽しみ。タイトルバックが始まった瞬間に勝負は決まってしまう。遅ればせながらDVDにて観た「ブロークン・イングリッシュ」は、出だしから大勝ちだった。鏡を前に、パーティーのために服を選ぶ仕草はウインゲイト・ペインの写真集「ミラー・オブ・ヴィーナス」から抜け出したかのよう。30代半ばの女性主人公はさわやかにメランコリックで、おまけにユーモラス。それなりのアヴァンチュールはあるものの、気がつけばいつも一人。本当の愛は、そう簡単には手に入らない。誰しも経験がある「konkatsu」のむなしさを誰よりも知っているのだ。監督のゾエ・カサベテスはジョン・カサベテスとジーナ・ローランズとの間に生まれた娘。両親の映画作りをじかに見て育ったわけで、回りの期待も大きかったでしょう。で、結果はOK。なにより女優の魅力が存分に引き出せていたと思う。着てた服も良かったし、音楽も悪くない、おまけにパリでゲンズブールの落書きだらけの家を訪ねるなんて小ネタも忘れないなど、痒いところに手が届きすぎだ。女優の名前はパーカー・ポージー。本名なのだろうか?ファニーだ。
映画は冒頭が楽しみ。タイトルバックが始まった瞬間に勝負は決まってしまう。遅ればせながらDVDにて観た「ブロークン・イングリッシュ」は、出だしから大勝ちだった。鏡を前に、パーティーのために服を選ぶ仕草はウインゲイト・ペインの写真集「ミラー・オブ・ヴィーナス」から抜け出したかのよう。30代半ばの女性主人公はさわやかにメランコリックで、おまけにユーモラス。それなりのアヴァンチュールはあるものの、気がつけばいつも一人。本当の愛は、そう簡単には手に入らない。誰しも経験がある「konkatsu」のむなしさを誰よりも知っているのだ。監督のゾエ・カサベテスはジョン・カサベテスとジーナ・ローランズとの間に生まれた娘。両親の映画作りをじかに見て育ったわけで、回りの期待も大きかったでしょう。で、結果はOK。なにより女優の魅力が存分に引き出せていたと思う。着てた服も良かったし、音楽も悪くない、おまけにパリでゲンズブールの落書きだらけの家を訪ねるなんて小ネタも忘れないなど、痒いところに手が届きすぎだ。女優の名前はパーカー・ポージー。本名なのだろうか?ファニーだ。
ベイカーパンツ
July 8th, 2009
 USアーミーのユーティリティ・パンツ、通称「ベイカーパンツ」を古着屋で見つけて、また買ってしまった。多分10本目くらいだろうか。といっても、初めて目にしたのは25年くらいも前だから、驚くほどの数ではないが、同じようなものをしつこく買ってしまう自分には少しあきれる。しかし、今回のは持っていないタイプ(脇にアジャスター付き)だったから仕方がない。ボタンの形が違うし、なによりコットン・サテンの風合いがクッタクタで、なんともいいパティーナ具合だったし、重みもある。肩凝り症で、おまけに椎間板ヘルニア持ちの身としては、重い服はいっさいオミットなのだが、こういう場合は別なのだ。高校生時分、はじめて買った古着のチノパンを見た母から「そんな菜っ葉ズボンを穿いて・・・」、といわれて以来、作業服に目覚めてしまった。今でも、外国に行って、ワークウェアを着こなした労働者を見るとつい嫉妬してしまう。でも、このパンツはもとはといえば米軍のもの。そういえば、持ってる10枚の中には血痕らしきものがうっすら残っているものもある。調べてみると、ベイカーパンツとは作業中に穿くものらしく、ということは非戦闘時に何か別のものが付着したと思いたいところなのだが、茶色に変色した跡はどうみても・・・。しかし、兵隊にとって、作業時っていつなのだろう。戦闘時とそうでない時の区別って本当にあるのだろうか。兵隊とは始終ワークタイムみたいなものではないのだろうか。何故そんなことを思ったかといえば、来月、ベトナムのホーチミンに行くことになったからだ。多分僕は、このベーカーパンツを穿いて南ベトナム陥落の地、旧サイゴンへ行くことになるだろう。
USアーミーのユーティリティ・パンツ、通称「ベイカーパンツ」を古着屋で見つけて、また買ってしまった。多分10本目くらいだろうか。といっても、初めて目にしたのは25年くらいも前だから、驚くほどの数ではないが、同じようなものをしつこく買ってしまう自分には少しあきれる。しかし、今回のは持っていないタイプ(脇にアジャスター付き)だったから仕方がない。ボタンの形が違うし、なによりコットン・サテンの風合いがクッタクタで、なんともいいパティーナ具合だったし、重みもある。肩凝り症で、おまけに椎間板ヘルニア持ちの身としては、重い服はいっさいオミットなのだが、こういう場合は別なのだ。高校生時分、はじめて買った古着のチノパンを見た母から「そんな菜っ葉ズボンを穿いて・・・」、といわれて以来、作業服に目覚めてしまった。今でも、外国に行って、ワークウェアを着こなした労働者を見るとつい嫉妬してしまう。でも、このパンツはもとはといえば米軍のもの。そういえば、持ってる10枚の中には血痕らしきものがうっすら残っているものもある。調べてみると、ベイカーパンツとは作業中に穿くものらしく、ということは非戦闘時に何か別のものが付着したと思いたいところなのだが、茶色に変色した跡はどうみても・・・。しかし、兵隊にとって、作業時っていつなのだろう。戦闘時とそうでない時の区別って本当にあるのだろうか。兵隊とは始終ワークタイムみたいなものではないのだろうか。何故そんなことを思ったかといえば、来月、ベトナムのホーチミンに行くことになったからだ。多分僕は、このベーカーパンツを穿いて南ベトナム陥落の地、旧サイゴンへ行くことになるだろう。
ホンマ・タカシの「たのしい写真」
July 3rd, 2009
 ホンマ・タカシの「たのしい写真」を読んだ。表紙タイトルの下に「よい子のための写真教室」というコピーがあって、平凡社とある。虫眼鏡を持つ手をレイアウトしたデザインと相まって、まるで古本屋でたまに見かける昔の教則本のようだ。内容の方も、写真の歴史から始まり、実践編へと、一見ありがちなハウツー本の体裁を取っているところが匂う。読んでみると案の定、すこぶる刺激的だった。まず冒頭で、「写真=真を写す」という日本語訳に異議を唱え、「photo=光、graph=描く」、つまり「光画」くらいの訳が妥当で、かなずしも「リアルさ」がマストではないと釘を刺す。その上で、絵画の代替として登場した写真が、ドキュメントやリアリズムを前提とした「決定的な瞬間」という時代に強い力を発揮し、その反動として「繰り返される凡庸な日常の光景」への転向を経てモダニズムを確立した、という説を述べている。その後はポストモダンの時代となり、「私的な物語」がテーマのひとつとなったというわけで、この流れはデザインの世界にも通じる仮説だと思う。結局、モダニズムの時代は「題材やテーマが大きかった」ということ。それが解体されて「小さな個人の物語」になったというわけ。つまり、写真にまつわる過度な思いこみを一旦括弧に入れてしまい、構造的に見てゆくという感じなのだろうか。おかげで、アラーキーや森山大道のことが少しわかったような気がした。ところで、後半、前述したビクトル・エリセの映画「マルメロの陽光」が「ドキュメンタリー=現実?」という項で紹介されていた。「時間が経過していること自体決定的で、もう二度と戻れない」という記述があり、「そうだよナー」と、ひとりごちる。
ホンマ・タカシの「たのしい写真」を読んだ。表紙タイトルの下に「よい子のための写真教室」というコピーがあって、平凡社とある。虫眼鏡を持つ手をレイアウトしたデザインと相まって、まるで古本屋でたまに見かける昔の教則本のようだ。内容の方も、写真の歴史から始まり、実践編へと、一見ありがちなハウツー本の体裁を取っているところが匂う。読んでみると案の定、すこぶる刺激的だった。まず冒頭で、「写真=真を写す」という日本語訳に異議を唱え、「photo=光、graph=描く」、つまり「光画」くらいの訳が妥当で、かなずしも「リアルさ」がマストではないと釘を刺す。その上で、絵画の代替として登場した写真が、ドキュメントやリアリズムを前提とした「決定的な瞬間」という時代に強い力を発揮し、その反動として「繰り返される凡庸な日常の光景」への転向を経てモダニズムを確立した、という説を述べている。その後はポストモダンの時代となり、「私的な物語」がテーマのひとつとなったというわけで、この流れはデザインの世界にも通じる仮説だと思う。結局、モダニズムの時代は「題材やテーマが大きかった」ということ。それが解体されて「小さな個人の物語」になったというわけ。つまり、写真にまつわる過度な思いこみを一旦括弧に入れてしまい、構造的に見てゆくという感じなのだろうか。おかげで、アラーキーや森山大道のことが少しわかったような気がした。ところで、後半、前述したビクトル・エリセの映画「マルメロの陽光」が「ドキュメンタリー=現実?」という項で紹介されていた。「時間が経過していること自体決定的で、もう二度と戻れない」という記述があり、「そうだよナー」と、ひとりごちる。
「マルメロの陽光」
June 27th, 2009
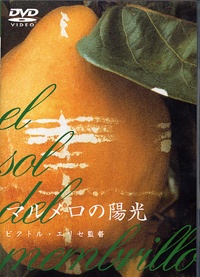 随分前に映画館で観た映画を、DVDでもういちど観たいと思うことがある。そういう場合、つい「あの感激をもう一度」と願ってしまうのだが、そうは問屋が卸してくれない。以前感じたにちがいない驚きが再現されることがないのは、久しぶりに会った昔の恋人に全然ドキドキしないことと似ている。もちろん、相手のせいではない。変わってしまったのは自分の方なのだろう。ところが、スペインの映画監督ビクトル・エリセが撮った「マルメロの陽光」は違っていた。17年ぶりに観たのだけれど、一層輝きが増したように思えた。実在の画家が、初秋から冬までの3ヶ月間、庭に育てたマルメロの実が朽ち果ててゆくまでを、定点観測のように丁寧に描く課程を追って行く。それだけの映画なのである。しかし、小津安二郎がそうであるように、一見淡々と見えながらも、隅々にまでみなぎる映画的感性には驚くほかはない。アトリエに舞い飛ぶ埃、刻々と変化する光。風の音や、犬の鳴き声、部屋の改装をする工事の槌音などの具体音。そして、これも実在の家族や、古くからの友人との語らいやユーモアを捉える的確なカメラ。すべてが、まるでテクストのように豊かだ。画家は始めに油彩を目指すものの、一瞬の陽光を捉えることの困難さに、「あきらめも肝心」とデッサンへと移行する。なんとイサギヨイことか。そして不思議なエンディング。あー、また最初から観ることにしよう。今度はパソコンの小さな画面で。
随分前に映画館で観た映画を、DVDでもういちど観たいと思うことがある。そういう場合、つい「あの感激をもう一度」と願ってしまうのだが、そうは問屋が卸してくれない。以前感じたにちがいない驚きが再現されることがないのは、久しぶりに会った昔の恋人に全然ドキドキしないことと似ている。もちろん、相手のせいではない。変わってしまったのは自分の方なのだろう。ところが、スペインの映画監督ビクトル・エリセが撮った「マルメロの陽光」は違っていた。17年ぶりに観たのだけれど、一層輝きが増したように思えた。実在の画家が、初秋から冬までの3ヶ月間、庭に育てたマルメロの実が朽ち果ててゆくまでを、定点観測のように丁寧に描く課程を追って行く。それだけの映画なのである。しかし、小津安二郎がそうであるように、一見淡々と見えながらも、隅々にまでみなぎる映画的感性には驚くほかはない。アトリエに舞い飛ぶ埃、刻々と変化する光。風の音や、犬の鳴き声、部屋の改装をする工事の槌音などの具体音。そして、これも実在の家族や、古くからの友人との語らいやユーモアを捉える的確なカメラ。すべてが、まるでテクストのように豊かだ。画家は始めに油彩を目指すものの、一瞬の陽光を捉えることの困難さに、「あきらめも肝心」とデッサンへと移行する。なんとイサギヨイことか。そして不思議なエンディング。あー、また最初から観ることにしよう。今度はパソコンの小さな画面で。
共有した場所
June 26th, 2009
 ジャン・ヴィゴ賞を受賞した「明るい瞳」というフランス映画をDVDで観る。見終わって、特典映像を覗くと、監督ジェローム・ボネルのインタヴューだった。映画後半の舞台となった場所について「何故ドイツを選んだのか」と質問されたとき、彼はこんな主旨のことを言っていた。「言葉が通じないところなら何処でも良かった。ただ、ここはドイツとフランスお互いが共有した場所だから・・・」と。舞台となった場所は映画の中では特定できないが、僕は勝手にアルザス地方を想像した。長い間ドイツとフランスで領土の獲得競争が繰り広げられ、普仏戦争や第二次世界大戦のフランス降伏に伴ってドイツに返還されたが、戦後はフランスが再占領し現在に至っている地域だ。いわば因縁の場所を、そんな風にいってしまうのがとても印象に残った。今でも世界中に「紛争地」と呼ばれる場所がたくさんある。言葉や文化が異なる他者同士が混在するところだ。お互いが排他的になりがちな場といってもいい。2年ほど前、買付でベルリンに3泊した際、ビックリしたことがある。夜中ホテルのベッドでテレビを付けるとヒットラーの映像が目に飛び込んできた。翌日はヒットラーの愛人エヴァ・ブラウンで、さらに3日目にはベルリン・オリンピックの記録映画を監督したレニ・リーフェンシュタールだった。特にドイツ終戦記念日ではなかったはずで、この国は普通にこんな番組を放送しているのだろうか、と不思議だった。それはまるで、過去の歴史を忘れまいとするドイツ・ジャーナリズムの決意のようだ。そんな思いが今のEUにつながっているのだと思う。
ジャン・ヴィゴ賞を受賞した「明るい瞳」というフランス映画をDVDで観る。見終わって、特典映像を覗くと、監督ジェローム・ボネルのインタヴューだった。映画後半の舞台となった場所について「何故ドイツを選んだのか」と質問されたとき、彼はこんな主旨のことを言っていた。「言葉が通じないところなら何処でも良かった。ただ、ここはドイツとフランスお互いが共有した場所だから・・・」と。舞台となった場所は映画の中では特定できないが、僕は勝手にアルザス地方を想像した。長い間ドイツとフランスで領土の獲得競争が繰り広げられ、普仏戦争や第二次世界大戦のフランス降伏に伴ってドイツに返還されたが、戦後はフランスが再占領し現在に至っている地域だ。いわば因縁の場所を、そんな風にいってしまうのがとても印象に残った。今でも世界中に「紛争地」と呼ばれる場所がたくさんある。言葉や文化が異なる他者同士が混在するところだ。お互いが排他的になりがちな場といってもいい。2年ほど前、買付でベルリンに3泊した際、ビックリしたことがある。夜中ホテルのベッドでテレビを付けるとヒットラーの映像が目に飛び込んできた。翌日はヒットラーの愛人エヴァ・ブラウンで、さらに3日目にはベルリン・オリンピックの記録映画を監督したレニ・リーフェンシュタールだった。特にドイツ終戦記念日ではなかったはずで、この国は普通にこんな番組を放送しているのだろうか、と不思議だった。それはまるで、過去の歴史を忘れまいとするドイツ・ジャーナリズムの決意のようだ。そんな思いが今のEUにつながっているのだと思う。