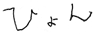身につけるわけでもない貝殻に興味を持った結果
October 11th, 2015
カウアイ島へ行ってみました。ハワイ諸島では最北に位置し、火山の隆起によって最初に出来た直径50kmほどの島です。東北側はいつも強い貿易風が吹いています。この風に乗ってやってきた西洋人で、はじめてこの島を発見したのがキャプテン・クックというわけです。
彼の銅像が小さな広場にポツンとあるワイメアは、国道沿いに古ぼけた西部劇のセットのような店がパラパラあるだけの、昼寝をしているような町。そんなレイドバックしたストリートに”COLLECTIBLES&Fine Junque”という看板の店を発見。たまらず、潜入。「収集品と優れたガラクタ」という名の通り、店内にはハワイらしいマルティ・カルチュアルで古ぼけた品々が一杯。若いころはきっとコニー・スティーブンスみたいにラブリーだっただろうと思われる白人のオバアちゃま店主が、キュートな英語でアレコレと丁寧に説明してくれるからうれしい。奇麗な石でできたフルーツと古い手吹きのガラスびんを購入。探していた”ニイハウシェル”はなかったけど「コレククターを紹介するわよ!」と言ってくれました。そのうえ別れ際に、これよかったらプレゼント、と司馬遼太郎のハードカヴァー本3冊セットを差し出されてビックリ。

「貝殻の宝石」といわれるニイハウシェルは、はじめて訪れたマウイ島のアンティック屋で遭遇して以来、気になって仕方がないシロモノです。直径はたった2~3ミリ、小さく美しい貝殻はニイハウ島という、とあるイギリス人が1864年にカメハメハ5世から、ピアノ1台と 10,000 ドルで買い取った小さな島でしか採れないと聞き、俄然興味が湧いたのかも。ところがその島は部外者は上陸禁止なのです。島民は所有者一家とそれを支える日系人の子孫を除けば全員ハワイ人だけ。現在もハワイ語を使用し、古来からの伝統的な生活を送っているらしく、いわばコミューンなのです。砂粒ほどのシェルは、見つけるのも一苦労ですが、粒を揃えて独特の手法で編み上げてレイ(ネックレス)やブレスレット、ピアスなどに仕上げるのにはとても手間ひまがかかるといいます。緑豊かなカウアイ島とは違い、乾燥したニイハウ島では、自給自足の生活をささえる、大切な収入源でもあるのです。今回は、そんな精緻でさまざまな表情を持ったニイハウシェルをめぐる旅だったともいえます。
そして、日本に戻ってから知ったニイハウ島にまつわる話があります。なんと、真珠湾攻撃の際、被弾したゼロ戦がニイハウ島に不時着したという事件があったのです。電話も電報もない島ですからオアフ島が突然日本軍の空襲を受けたことを島民は知らない。何が起こったのか、英語を知らない日本兵と、ハワイ語しかしゃべらない島民とのコミュニケーションは、島の日本人に頼らざるをえなかったようです。そのうちに、事態が明らかになり、アメリカと日本が戦争状態に入ったことがわかってくる。そして、ゼロ戦に残っていた暗号書類などを守ろうとした日本兵との間に諍いが起こり、結局彼は殺されてしまいます(一説には自殺という説もあります)。事件後、通訳の役目をしたニイハウ島の日系人はアメリカではなく日本の見方をしたということで「敵性勢力」として見られてしまうことになります。そしてそれは、その後ハワイ全体の日系人へとその影響が及んでゆくことの前兆だったのです。
そんなわけで、自分が身につけるわけでもない貝殻に興味を持った結果、ハワイという”楽園”に埋もれていた戦争の足跡に触れることになったのです。

人生はジェラートみたいなもの。
July 23rd, 2012
 「あっ、カナちゃんだ!」と思ったが、いくら神出鬼没の彼女でも、まさか今ミラノにいるとは考えにくい。地図を片手に目当ての店を探していたぼくは、通りの反対側を自転車に乗って走り去ったアジア系女性を目で追った。それにしても独特のファッションとボヘミアンっぽい雰囲気が彼女にソックリ。まあ、広い世界には似た人はいるもんだし、とサクッと片付け、番地探しに集中した。その店は、立つ前日dieceの田丸さんに電話して「久々のミラノなので何処かおすすめを」と乞い教えてもらったもの。フラフラとなんとかその番地に到達したが、住宅街にあるのでとても分かりにくい。店の看板やサインもなく、アパルトマンの名札のなかにようやくそれらしき名前を見つけ、何度か呼び鈴を鳴らして中に入った。
「あっ、カナちゃんだ!」と思ったが、いくら神出鬼没の彼女でも、まさか今ミラノにいるとは考えにくい。地図を片手に目当ての店を探していたぼくは、通りの反対側を自転車に乗って走り去ったアジア系女性を目で追った。それにしても独特のファッションとボヘミアンっぽい雰囲気が彼女にソックリ。まあ、広い世界には似た人はいるもんだし、とサクッと片付け、番地探しに集中した。その店は、立つ前日dieceの田丸さんに電話して「久々のミラノなので何処かおすすめを」と乞い教えてもらったもの。フラフラとなんとかその番地に到達したが、住宅街にあるのでとても分かりにくい。店の看板やサインもなく、アパルトマンの名札のなかにようやくそれらしき名前を見つけ、何度か呼び鈴を鳴らして中に入った。
中庭には様々な植物や椅子、家具などが無造作に置かれていて、それがとてもいい雰囲気。応対してくれた女性マネージャーによると、サローネの時期にはここでイヴェントやパーティーも行われるとのこと。と、その時現れたのが、くだんのカナちゃんそっくりな女性。「ど~も」と声をかけたら「さっき、歩いてましたよね」と、お互い認知のご挨拶。聞くと、ここの庭の手入れをしているとのこと。ガーディアンなのである。話しだしたらキリがないところや、ちょっと舌っ足らずの早口かげんはまさに「ミラノのカナちゃん」だった。なにより(モチロン)親切心からの「お節介さ」もそっくり。美味しくて気の置けないランチの店を教えてもらったりもした。昔に比べて、海外でウゴメク若人が少なくなったと思っていたのだけれど、そんなこともないようだ。人生はジェラートみたいなもの。溶けてしまう前に舐め尽くす時間は思っているより短い。
コルビュジエ眼鏡が入荷しました。
July 12th, 2012
 中学でかけるハメになったのだから、メガネ歴はそれなりに長い。度が進むたびに新天町のメガネ屋に行き、アレでもないコレでもないと言って母を困らせたものだ。丸メガネを好きになったのは『ホワイト・アルバム』の頃のジョン・レノンのせいなのか、それ以前ジョン・ゼバスチャンだったか?大学時代には肩まで伸ばしたロングヘアーにまん丸のメタル・フレームでベルボトムというピースなイデタチだった。ボストンやウエリントン型のセル・フレームも悪くないなー、と思ったのはウディ・アレンの『アニー・ホール』を観たころだったが、残念ながら町のメガネ屋には見当たらなかった。唯一、上野の「白山眼鏡」には各種そろっていてうれしかった。で、ある日まん丸のセルフレームをかけてみると藤田嗣治になった。それ以来、丸メガネをかけているのだが、最近はちょっと大きめの丸メガネでデヴィッド・ホックニー気分だったりしている。そのフレームはパリのマレ地区にあるメガネ屋で見つけたもので、太いセルロイドとあまり今っぽくないデザインがいいと思う。そこからは、写真のようなモデルも出ていて、テンプル裏に“MOD. LE CORBUSIER” とある。写真で見比べると、たしかにコルブ氏がかけていた眼鏡である。そういえば“MERCI” のカフェの女性スタッフもこれをかけていたっけ。ちょっと文学少女っぽくもある。気になる人はorganに来て試してみてください。26250円なり。
中学でかけるハメになったのだから、メガネ歴はそれなりに長い。度が進むたびに新天町のメガネ屋に行き、アレでもないコレでもないと言って母を困らせたものだ。丸メガネを好きになったのは『ホワイト・アルバム』の頃のジョン・レノンのせいなのか、それ以前ジョン・ゼバスチャンだったか?大学時代には肩まで伸ばしたロングヘアーにまん丸のメタル・フレームでベルボトムというピースなイデタチだった。ボストンやウエリントン型のセル・フレームも悪くないなー、と思ったのはウディ・アレンの『アニー・ホール』を観たころだったが、残念ながら町のメガネ屋には見当たらなかった。唯一、上野の「白山眼鏡」には各種そろっていてうれしかった。で、ある日まん丸のセルフレームをかけてみると藤田嗣治になった。それ以来、丸メガネをかけているのだが、最近はちょっと大きめの丸メガネでデヴィッド・ホックニー気分だったりしている。そのフレームはパリのマレ地区にあるメガネ屋で見つけたもので、太いセルロイドとあまり今っぽくないデザインがいいと思う。そこからは、写真のようなモデルも出ていて、テンプル裏に“MOD. LE CORBUSIER” とある。写真で見比べると、たしかにコルブ氏がかけていた眼鏡である。そういえば“MERCI” のカフェの女性スタッフもこれをかけていたっけ。ちょっと文学少女っぽくもある。気になる人はorganに来て試してみてください。26250円なり。
「ロカ岬」
July 11th, 2012
 「ロカ岬」はポルトガルでも人気の観光スポット。なにしろユーラシア大陸最西端に位置するわけで、反対の東端(の沖合の島)からやってきた身としても気にならないわけがなく、先述したシントラという町から乗合バスに飛び乗った。ダラダラと海に向かって下る田舎道を50分くらいだったか、ずーっと乗りっぱなしの観光客と、乗っては降りる地元の人々が半々という感じだった。中学生とおぼしきおマセな女の子達が学校前の停留所から乗り込んで、ひとしきり車内で騒いだかと思ったら、一人、又一人と下車していった頃、開けた草地の向こうに大西洋が見えてきた。
「ロカ岬」はポルトガルでも人気の観光スポット。なにしろユーラシア大陸最西端に位置するわけで、反対の東端(の沖合の島)からやってきた身としても気にならないわけがなく、先述したシントラという町から乗合バスに飛び乗った。ダラダラと海に向かって下る田舎道を50分くらいだったか、ずーっと乗りっぱなしの観光客と、乗っては降りる地元の人々が半々という感じだった。中学生とおぼしきおマセな女の子達が学校前の停留所から乗り込んで、ひとしきり車内で騒いだかと思ったら、一人、又一人と下車していった頃、開けた草地の向こうに大西洋が見えてきた。
バスを降り、カフェテリアでよく冷えたビールの小瓶を買って岬の突端へと歩いた。荒涼とした岩場は一面のお花畑で海からの強風が吹きまくっている。花々は見たこともないような種類で、低くへばりつくように様々な色が咲き誇っている。風で帽子が飛ばされないように気をつけながら、写真で見たことがある「ここに地果て、海始まる」と刻まれた例の大きな十字架の向こう側へ行ってみると、突然視界が200度くらいに広がった。
わずかにアールを描いた水平線と空との境界がうっすらと煙り、なんだかあの世の景色みたいに幻惑的。ここからそのまま西へ向かえば、確かニューヨークに到達するはずだ。この未知の海原を越えて新大陸を目指した男どもは、本当に向こう見ずで野心タップリだったに違いない。なにしろ彼らは喜望峰を周りインド洋からマラッカ海峡を抜けはるか種子島まで到達した。そう「黄金の国ジパング」にコンタクトした初の南蛮人となったわけだ。
なんとかこの景色をカメラにおさめようとアレコレしていると、突然オジサンが僕ら二人を撮ってあげようかと声をかけてきた。お言葉に甘えてi Phoneのシャッター位置を教えてあげていたら「わかった、ここだね」と言った瞬間が残っている。レイバンのサングラスが似合う「良きバテレンさん」である。
こりゃー気持ちいいい。
June 28th, 2012
 8世紀にムーア人が造ったという砦のもっと上、標高500mの山のてっぺんにペーナ城というポルトガル王の夏の離宮がそびえている。「一大パノラマ」という言葉に弱いぼくは、まずはそこを攻め、然る後にムーアの城跡を訪ねる作戦に出た。
8世紀にムーア人が造ったという砦のもっと上、標高500mの山のてっぺんにペーナ城というポルトガル王の夏の離宮がそびえている。「一大パノラマ」という言葉に弱いぼくは、まずはそこを攻め、然る後にムーアの城跡を訪ねる作戦に出た。
ガイド本によると、ペーナ城は19世紀にドイツのルードヴィッヒ2世のいとこが建築を命じたとある。イスラム、ゴシック、ルネッサンスなどの様式が混在した城らしい。ビスコンティの映画で見る限り、ルードヴィッヒの趣味はかなりビザールだった記憶があって、どんな具合なのかちょっと興味がある。
狭い山道を、猛烈な勢いで駆け登るバスのおかげで、あっという間に到着。傾斜のきつい庭園の坂を登り切ると、目の前に映画のセットみたいな風景が目に飛び込んできた。城の内部に入ってみると、中国趣味や、トルコ風、果てはトランプルイユまで、これまた各部屋がテーマ別にしつらえてある。もちろん調度品もいかにも手の込んだ工芸品ばかり。帝国主義に至る時代の王様達が、いかにエキゾティックな世界にハマっていたかを垣間見る思い。元祖VIPによるプライベート・ディズニーランドを見る思いだった。唯一面白かったのは台所。もちろんかなり広いのだけれど、鍋、窯、バスケット、などの道具類には生活を感じた。ちょっとしたブロカントへ紛れ込んだような気分で「もし買い付けるとすれば、あの手作りっぽいテーブルかな…」などと妄想に耽る。
ふと気が付けば、閉館まであとわずか。文句言いつつ、結構な時間を過ごしてしまったようだ。この様子ではムーア人の砦は諦めるしかない。最後に城壁の上をグルっと回って帰ろうとしたら、見えるではありませんか、はるか眼下に大西洋を睥睨するかのような古城が!こりゃー気持ちいいい。
オッと、これは、どう見てもイスラム世界である。
June 24th, 2012
 買い付け旅では観光らしい観光をすることはないのだが、今回はリスボンから列車で1時間ほどにあるシントラという所へ行ってみた。前々から気になっていたムーア人の古城があるからである。さて、謎に満ちた彼らの足跡はいかに?
買い付け旅では観光らしい観光をすることはないのだが、今回はリスボンから列車で1時間ほどにあるシントラという所へ行ってみた。前々から気になっていたムーア人の古城があるからである。さて、謎に満ちた彼らの足跡はいかに?
ムーア人のことで印象に残っているのは『トゥルー・ロマンス』という(またまた)映画。デニス・ホッパー扮する警官がクリストファー・ウォーケン扮するマフィアの親玉に向かって「その昔ムーア人達がお前の祖先とファックしたおかげでイタリア人は黒髪と黒い目になったんだ」と罵倒してあっさり撃ち殺されるシーンである。そしてもうひとつ、随分前に『モーリス』という映画がヒットした際、イギリスに多いモーリスという名前の語源がムーアであることも。
ムーア人がイベリア半島を席巻したのは8世紀くらい。イスラム化した北アフリカのベルベル人である彼らは、西欧に先駆けた様々な知恵を携えていたようだ。たとえば星々を観測して方角や位置を知る方法は、砂漠を交易する民として不可欠であり、それが航海術として地中海を帆船で自由に交通することを可能にしたはずで、ジブラルタル海峡を渡るなんてオチャノコサイサイだっただろう。その後、そんな先端技術を利用したポルトガルが世界に先駆けて、いわゆる大航海時代に乗り出す下地ともなったと考えられている。なにせ、ローマ帝国はまだガレー船という人力でオールを漕いでいた時代、イスラムのほうが断然進んでいたわけである。とまあ、ヨーロッパが好きな割には、西欧からの視点による歴史観に少々異議がある身として現場検証的な興味もあったのだ。
王侯貴族の城館や金持ちの別荘が点在する静かな山間の町シントラは、イギリスの詩人バイロンをして「この世のエデン」と言わしめたらしい。坂道をしばらく歩くと、「ムーアの泉」があった。オッと、これは、どう見てもイスラム世界である。
ドロボー市。
June 22nd, 2012
 「ドロボー市」といえば、パリのモントルイユで毎週末に開かれるのが有名だ。日用品を始めとしたガラクタも多く、その昔は盗品なども出回っていたらしい。中には「めっけ物」もあったりするが、見つけるのには相当の時間と忍耐を要する。もちろん、混雑を狙った現役のドロボーさんも徘徊しているので油断はできない。
「ドロボー市」といえば、パリのモントルイユで毎週末に開かれるのが有名だ。日用品を始めとしたガラクタも多く、その昔は盗品なども出回っていたらしい。中には「めっけ物」もあったりするが、見つけるのには相当の時間と忍耐を要する。もちろん、混雑を狙った現役のドロボーさんも徘徊しているので油断はできない。
そんなわけで、リスボンのドロボー市にもあまり期待せずに出かけたのだけれど、予想以上に面白かった。キリスト教系のモノを始め、イスラム風手描きのアズレージョ、東洋を意識した陶器類、錫のコップなど、いずれもこの国の古い歴史と多様な文化を感じさせてくれる。値段も悪くない。それにしても日差しが強い。1時間も探索していると、手の甲がうっすら日焼けしているのが分かるほどだ。
そんな中で、いわくあり気な5,6個の土くれめいたものを置いた小さなテーブルに足が止まった。聞くと、どれもが大西洋に沈んだ船から引き上げられたローマ帝国時代の遺物だという。一生懸命英語で説明するおじさんは、いたって真面目そうである。自分で作ったという小さな冊子には、沈没船が見つかったイベリア半島沖の場所がたくさん載っている。僕が興味を持った塑像は、ちょっとリサ・ラーソンのスタジオものを思わせる風情があって、古いコインと一緒にいただくことにした。腰布をまとっただけの石の像はすっかり彩色も薄れ、少し湿り気があって、触るとひんやり、そして思った以上に持ち重みがした。
リスボンの過ごし方。
June 21st, 2012
 初めて訪れたリスボンはまぶしい5月の陽光のなかだった。アラン・タネールの『白い街』やヴィム・ヴェンダースの『リスボン物語』の映画のシーンみたいに、古いアズレージョ(イスラム風タイル)の壁には洗濯物がハタハタと気持ちよさそうに風にたなびいていた。おかげで、空港からのタクシー代をボラレたうえに、大荷物を抱えてホテルまで3ブロックも歩く羽目になったことなど、すっかり帳消しになった。
初めて訪れたリスボンはまぶしい5月の陽光のなかだった。アラン・タネールの『白い街』やヴィム・ヴェンダースの『リスボン物語』の映画のシーンみたいに、古いアズレージョ(イスラム風タイル)の壁には洗濯物がハタハタと気持ちよさそうに風にたなびいていた。おかげで、空港からのタクシー代をボラレたうえに、大荷物を抱えてホテルまで3ブロックも歩く羽目になったことなど、すっかり帳消しになった。
焼いただけのイワシとフレッシュな白ワインがとても美味しかった。檀一雄が好きだったという”Dao”というワインも良かったけど、昼間からやるには何と言っても冷えた白がいい。路地裏の大衆食堂で、小さなピシェ(2.5ユーロくらい)と白身魚のトマト味雑炊(パクチーが載ってる)をぱくつく。悪くないリスボンの過ごし方だ。
ただし、28番線の古ぼけたトラムにはご用心。僕はあっさりスリに遭いました。買付け旅を始めて15年、初の体験でした。アップダウンが激しく、眺めのいいところや旧市街を通る人気の路線が、スリの活躍の場であることはガイドブックで読んでいたのだけれど、まったくもって情けない。ただでさえ混んでいる車内で、年寄りを通すために道を開けてくれと強引に体を押し付ける男に気を取られている間に、別の男にズボンに入れていた現金を抜かれてしまったのです。どうやら、年寄りも含めた3人は一味だったようです。
だからと言って、この街が嫌いになることはなかったから不思議。次の日は、ケロッとして泥棒市へと向かいました。
キム・ヘジョンさんの器
May 4th, 2012
 来週月曜から始まる”ash (satsuma design & craft) at organ ”に向けて、鹿児島から荷物が続々到着。どの商品もそれぞれに興味深く、なかでも“CHIN JUKAN POTTERY”から届いたキム・ヘジョンさんの焼き物に驚いた。どれもビッシリと貫入(かんにゅう)が入っている。まるで細かな蜘蛛の巣のような模様(というと、貫入が苦手な人は腰が引けそうなのだ)が、器自体の美しい形に格別の表情を与えることに成功している。1200度くらいの高温で焼きあがった作品が冷えてゆく過程で、表面が溶けてガラスのようになった釉薬が収縮してヒビのような状態になって固まるのが貫入なのだが、使ってゆく過程でゆっくり貫入が進むこともあり、昔の茶人などは茶渋やシミが入り込んだ抹茶茶碗などを「景色」として楽しんだのは御存知の通り。そこまでではないにしても、ぼくが「貫入好き」になったきっかけは李朝の茶碗。8年ほど前だったか、ソウルへ出かけてアンティック屋めぐりをしたこともあった。でも、キムさんの器の魅力はなんといっても色と形。この柔らかな黄色もいいのだが、透き通るような青磁に浮き出る貫入はとても美しい。そう、葉脈のようだと言い直しておこう。
来週月曜から始まる”ash (satsuma design & craft) at organ ”に向けて、鹿児島から荷物が続々到着。どの商品もそれぞれに興味深く、なかでも“CHIN JUKAN POTTERY”から届いたキム・ヘジョンさんの焼き物に驚いた。どれもビッシリと貫入(かんにゅう)が入っている。まるで細かな蜘蛛の巣のような模様(というと、貫入が苦手な人は腰が引けそうなのだ)が、器自体の美しい形に格別の表情を与えることに成功している。1200度くらいの高温で焼きあがった作品が冷えてゆく過程で、表面が溶けてガラスのようになった釉薬が収縮してヒビのような状態になって固まるのが貫入なのだが、使ってゆく過程でゆっくり貫入が進むこともあり、昔の茶人などは茶渋やシミが入り込んだ抹茶茶碗などを「景色」として楽しんだのは御存知の通り。そこまでではないにしても、ぼくが「貫入好き」になったきっかけは李朝の茶碗。8年ほど前だったか、ソウルへ出かけてアンティック屋めぐりをしたこともあった。でも、キムさんの器の魅力はなんといっても色と形。この柔らかな黄色もいいのだが、透き通るような青磁に浮き出る貫入はとても美しい。そう、葉脈のようだと言い直しておこう。
おとといポップス#8 ”ザ・バンドに肉薄したつもり”
April 25th, 2012
 バンドを結成するからには、名前が必要だった。随分考えたのだけれど、どれもピンと来ない。ある日、いつものように高円寺駅の高架下をすり抜けてムーヴィンへ向かう途中で古本屋のワゴン100円均一を漁っていた。すると、わら半紙のいかにも古めかしい薄っぺらな本が流し目をくれた。粗末な印刷だったが、確かに『葡萄畑の葡萄作り』と読めた。なんてイカレたタイトルなんだ、と思った。だって、葡萄畑で葡萄を作るのはアタリマエでしかない。作者はジュール・ルナールだった。読んだことはないが『にんじん』という赤毛の子供を主人公にしたフランスの小説を書いた人である。ページをめくると、エッセイとも警句ともつかない短い文章が並んでいた。そして、どうやら作者自身によるいたずら書ききみたいな挿絵が添えられている。たとえば〈ごきぶり〉というタイトルには黒い物体がチンマリと描かれ、「鍵穴みたいなものである」という文章だけという具合なのだ。その瞬間、名前が決まった。しかし、できるだけ意味のない名前を選んだつもりだったが、もちろんザ・バンドという、当時彼らがコミューンみたいな暮らしをしていたウッドストック村の住民から名付けられた名前にかなうものではなかった。その村には他にバンドはいなかったという単純明快な理由もあったのだろうが、「自分たちのためだけに音楽を演る」という彼らの姿勢には、これ以上の名前がなかったのだと思う。そのバンドのドラマーでヴォーカリストだったレヴォン・ヘルムが亡くなった。5人のうち、唯一のアメリカ人、それも生粋の南部人の存在は、どちらかと言えばペシミスティックなザ・バンドの音楽にまっとうなドライブ感を与えてくれた。鈴木慶一氏もツイッターで言っていたように、これで3人のヴォーカリストはすべていなくなってしまったわけである。写真は1972年くらい、ツアー先で撮った葡萄畑。ザ・バンドに肉薄したつもりなのである。
バンドを結成するからには、名前が必要だった。随分考えたのだけれど、どれもピンと来ない。ある日、いつものように高円寺駅の高架下をすり抜けてムーヴィンへ向かう途中で古本屋のワゴン100円均一を漁っていた。すると、わら半紙のいかにも古めかしい薄っぺらな本が流し目をくれた。粗末な印刷だったが、確かに『葡萄畑の葡萄作り』と読めた。なんてイカレたタイトルなんだ、と思った。だって、葡萄畑で葡萄を作るのはアタリマエでしかない。作者はジュール・ルナールだった。読んだことはないが『にんじん』という赤毛の子供を主人公にしたフランスの小説を書いた人である。ページをめくると、エッセイとも警句ともつかない短い文章が並んでいた。そして、どうやら作者自身によるいたずら書ききみたいな挿絵が添えられている。たとえば〈ごきぶり〉というタイトルには黒い物体がチンマリと描かれ、「鍵穴みたいなものである」という文章だけという具合なのだ。その瞬間、名前が決まった。しかし、できるだけ意味のない名前を選んだつもりだったが、もちろんザ・バンドという、当時彼らがコミューンみたいな暮らしをしていたウッドストック村の住民から名付けられた名前にかなうものではなかった。その村には他にバンドはいなかったという単純明快な理由もあったのだろうが、「自分たちのためだけに音楽を演る」という彼らの姿勢には、これ以上の名前がなかったのだと思う。そのバンドのドラマーでヴォーカリストだったレヴォン・ヘルムが亡くなった。5人のうち、唯一のアメリカ人、それも生粋の南部人の存在は、どちらかと言えばペシミスティックなザ・バンドの音楽にまっとうなドライブ感を与えてくれた。鈴木慶一氏もツイッターで言っていたように、これで3人のヴォーカリストはすべていなくなってしまったわけである。写真は1972年くらい、ツアー先で撮った葡萄畑。ザ・バンドに肉薄したつもりなのである。